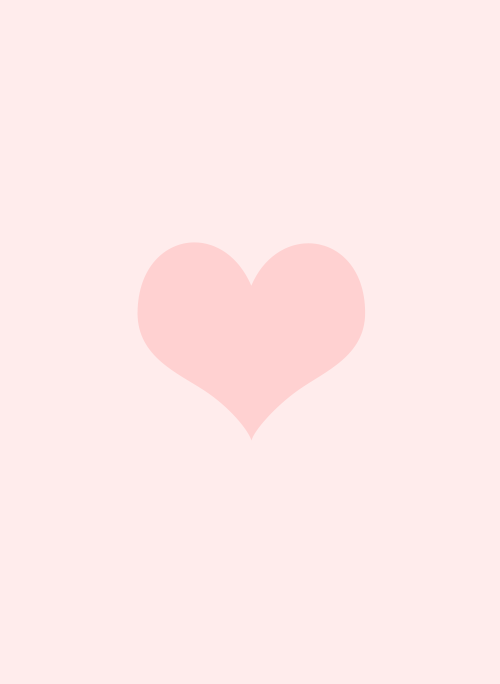「えっ、嘘!」
「やっぱり陽葵ちゃんは頭いいよねぇ」
近くにいた相川さんと日々ちゃんも、話に便乗するようだ。
「どうすればそんな点数とれるんだろう……」
「雫には無理だよ」
真剣に考えていたらしい月野さんに対して、少し失礼な物言いの鶴本くん。
最近は、この6人でいるでいることが多い。
仲良くなってから知ったことだけれど。
こう見えて錦戸くんと鶴本くんは同じ中学校だったらしい。
確かに、マイペースな鶴本くんの扱いに慣れている。
その点では錦戸くんが1番長けているように思う。
そして、月野さんと鶴本くんは想い合っていることは確かなのにお互いに気づいていない。
そんな個性豊かな友達ができて、毎日が充実していた。
たったひとつ、天音先輩に会えていないことを除けば─────。
◇◆◇
「呼び出してごめん、音中さん」
放課後の教室。
今の時期は日が沈むのも早いから、もう既に少し薄暗い。
理由はわからないけれど、私は今……錦戸くんとふたりきりだ。
「何かあったの?」
こんな風に面と向かって呼び出されることなんてなかったから、なぜだか緊張する。
どんな話をされるんだろうか。
勉強?友達?
想像もつかない。
けれど、真面目で社交的な彼がわざわざ呼び出したということは。
何か大切な用があることだけは間違いないだろう。
「あの……。
音中さんのことが、好きですっ……!」
……はい?
今、とんでもない言葉が聞こえたような気がした。
きっと私がおかしな妄想をしているだけなのだろうけれど。
それにしては、彼の顔が赤い。
「俺と付き合ってくれませんか?」
「え……?」
今までにないくらいの素っ頓狂な声を出してしまった。
嘘でしょう?
本当に、こんなに心臓に悪いことはやめてほしい。
まさか……あの錦戸くんが、私のことを好き?
これは一体どんな経緯があるのだろうか。
「最初は隣の席だから話しかけていただけだった。
でもいつからか、音中さんのことが気になっていたんだ」
これが、よく相川さん達が騒いでいる……告白……。
誰が誰に告白した。
そんな噂を耳にすると、必ず赤い顔をして相川さんは騒ぎだす。
私は今までされたことがなかったから、いつもその様子を冷めた目で見ていたけれど。
そんなものを、今私がされているなんて……。
「音中さんはきっと友達としか見ていないよね。
それはわかっているけれど……俺のこと、男として見てほしい」
男として、だなんて。
こんなにまっすぐな想いを伝えられたのは初めてで、戸惑ってしまう。
私が困惑していると、彼はフッと笑った。
「困らせてごめんな。
……家まで送るよ、一緒に帰ろう」
「……うん」
急かされるようにそう言われて、彼が家まで送ってくれることになった。
気まずい雰囲気のままなんて会話が続かないんじゃないか。
そう思ったけれど、彼はそれを押し切って「大丈夫」と言う。
こんなに親切にされると、なんだか申し訳なくなってしまう。
それを伝えると。
「俺が音中さんと一緒にいたいだけだから」
と、なんとも紳士らしい答えが返ってきた。
初めて私に告白してくれた人。
クラスに馴染めていなかった私を、初めて『面白い』と言ってくれた人。
彼は、このクラスでの居場所をくれた、そんな人。
錦戸くんと付き合ったら、毎日がもっと楽しくなるのかもしれない。
夢のようにキラキラした、華々しい日々が待っているのかもしれない。
けれど、私には……。
どうしても心から離れない人がいる。
────話さなくなってからも、天音先輩への気持ちが……消えない。
芽生えてしまった感情は、そう簡単に消せなかった。
私はお姉ちゃんの彼氏を好きになってしまった。
許されるはずのない恋なのに、こんなにも諦められないなんて。
こんな状態で返事をしても、きっと錦戸くんを困らせるだけだ。
それなら、しっかりと考えて私の意思を彼に伝えよう。
それが、私の辿り着いた答えだった。
◇◆◇
「陽葵、話があるの」
「……何?」
帰宅後、どうしてかお母さんに引き止められた。
「夏休みに家に来た、奏汰くんって覚えている?」
「あぁ、うん」
────ドキッ。
まさかお母さんの口から天音先輩の名前が出るなんて。
いろいろな意味でドキッとしてしまった。
「奏汰くん、学校ではどんな感じかわかる?
まだピアノは弾いていないのかしら」
どうして急にこんなことを聞いてきたのかはわからない。
それでも、お母さんも彼を我が子のように気にかけている。
それはきっとお姉ちゃんと付き合い始めたときから変わらないんだと思う。
「……ピアノは弾いていない。
学校では、いつも作り笑いだよ」
「そう……」
表現が悪いかもしれないけれど、そう見える。
彼は本当の自分を見せようとしたことがないはずだ。
でも、お母さんは明るい顔で私の顔を見て口を開いた。
「陽葵、お願いがあるの」
◇◆◇
そんなお母さんの要望に応えるために、私は今。
天音先輩とふたりで歩いている。
会話はない。
それでも、目も合わせてくれないときより心が軽い。
「……どうしてこうなったんだ」
初めて口を開いたかと思うと、不服そうに見下ろされる。
「私の母が言い出したんです。
天音先輩と私でお姉ちゃんの墓参りに行ってみないか、って」
お母さんからのお願い。
それは、まだお姉ちゃんのことを気に病んでいる天音先輩と。
墓参りに行くことだった。
私にとっては好都合。
天音先輩が嫌がることは目に見えていた。
でも、きっかけがあれば話してくれるかと思い。
あれからすぐに彼の家へ電話をかけて、約束を取りつけた。
あと数日で冬休み。
空からは少し雪が舞っていた。
この作家の他の作品
表紙を見る
本を読むことが好きな日野くんは。
なぜか今日も
私が持っている恋愛小説を読みます。
「……変なやつ」
「七草さんって、こういうことされたいの?」
「七草さんは、俺のだから」
口数は少ないのに。
その言葉に、行動に。
全てに、私の心はつかまれる。
ねぇ、なんでですか?
今、何を思ってますか?
私、日野くんの心が知りたいです。
ポジティブな真面目ちゃん
七草弥生(ななくさやよい)
×
口下手な隠れイケメン
日野大雅(ひのたいが)
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆
2019年6月18日~
野いちご編集部オススメ作品に掲載されました!
2019年6月20日
野いちご総合ランキングにランクイン!
本当にありがとうございます♡
表紙を見る
「大丈夫」
だなんて、なんて儚い言葉だろう。
今も君は俺のために。
苦しい気持ちを押し殺して
泣いているというのに。
ねぇ、この出会いは間違いだったかな。
恋なんてしなければ良かったかな。
後悔しても、泣いても、
明日は必ずやってくる。
また立ち上がることができれば
きっと笑えるから。
だから君も、最後に笑顔を見せてよ。
愛して、愛されて、それでも繋がらない心。
この恋の形は歪だった。
でも、誰もが懸命に恋をして、
不器用に今を走り続けていた。
これは、絶対に忘れられない、
俺の桜色の思い出。
表紙を見る
俺の住む世界には、いろいろな人がいる。
「よくここに来るの。
ひとりになりたいときにね」
傷つき、誰にも相談せずに、
自分を守ろうとする人。
「俺は、逃げてばかりなんだ……」
親とぶつかり、
自分の気持ちを見失いかけている人。
「アイツは知らねーよ。
言わないつもり」
誰かの幸せのために、自分の心を削って
守り抜こうとする人。
「……俺、ずっと後悔していた」
誰かを救うための優しい嘘で、
相手を逆に傷つけてしまった人。
「お前なんて……っ!
死んじゃえばいいのに!!」
そう言って─────俺の前から姿を消した人。
そして……。
「もう、わかんねーや……」
見えない過去に怯えて、
今日を歩けないでいる人。
ここにいる全員が “ 嘘つき ” で。
誰よりも懸命に、甘酸っぱい
青春時代を過ごそうとしていた。
だから、何があっても
神様のイタズラなんかに
負けちゃダメなんだ。
ヒミツの夜、蛍の光の中で。
俺達の嘘は全て、真実と交わる。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…
この作品をシェア
キミの音を聴きたくて
を読み込んでいます