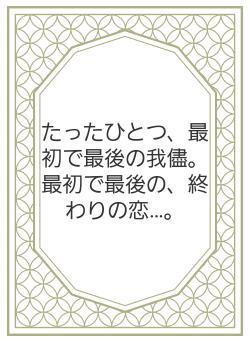かつん。
ソレが合図のように、俺は小説から目線を上げる。
視界にしっかりと彼女の姿を捉えてから、にこりと微笑んで迎えた。
「ごめんね?」
と、申し訳なさそうに話し掛けて来る彼女を庇うように、俺は笑顔のままで大丈夫ですよ、とタオル地のハンカチを手渡した。
…。
良かった。
こんな雨の日でも、逢いに来てくれたんだ…。
そう思いながら、彼女へハンカチを向けると案外あっさりと「ありがとう」と言われ、そのまま俺のハンカチは彼女の守へと移動する。
咄嗟に…一瞬だけ…「ハンカチになりたい」なんて不埒なことを思ったけれど、『ソレじゃ本当の変態だろ!』と心の中で突っ込んでなんとか自制した。