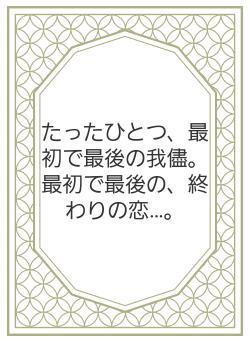その定まらない視線で、ハッと思う。
そうだ。
こんな時簡に、自分の部屋で、好きな人と二人きり…。
そう考えたら、ドキドキしてきてしまい、私も彼の顔が直視できなくなる。
「さ、寒かったでしょ?これ、飲んで?少しは暖まると思うから…」
さっと、紅茶を差し出して、私は、彼の真向かいに座り、その辺に置いておいたクッションをぎゅうと抱き締める。
そうすると、少し考え顔をした彼が私に微笑み掛けてきた。
「あやめさん?」
「ん?」
「隣、来てくれないんですか?」
「……ん。待って、今いき、ます…」
カァーと顔に体中の血が昇っていくのを感じる。
でも、彼の隣が心地良いのは誰よりも知っているから…つつつ…とクッションを持ったまま移動して、そっと彼の横に座った。