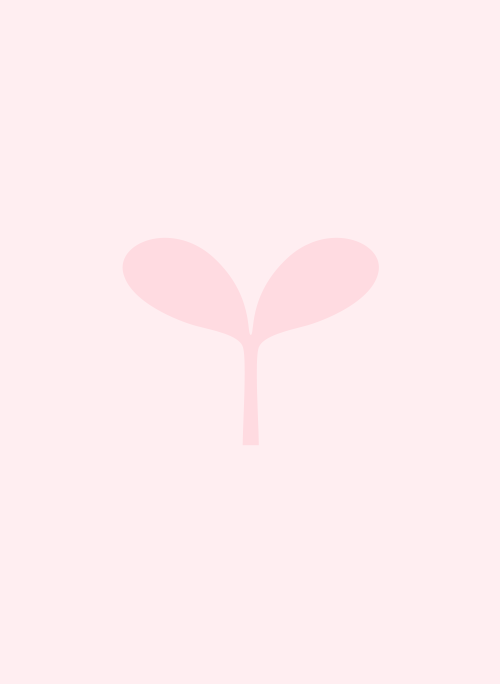「えーと、大人っぽくて頼りになるところかな」
「へぇー……確かに一応、一家の支えになってるけど。兄貴、そんな事言われてどうよ?」
ニヤニヤ誠は笑っている
「ばか、照れるだろ」
そんなやり取りをしている内に学校に辿り着いた
「じゃあ、行ってくる」
「あぁ、がんばれよ。なずなちゃんも」
「はい、行って来ます。送ってくれてありがとうございました」
いつも交わすキスは人目があるのでしなかった
そのせいか、少し切なくて寂しさが後に残った
みんなに注目されるのが嫌だから、少し校門の手前で降ろして貰ったが、すでに登校している生徒で溢れていて焼け石に水だった
黄色い声の渦のなかにわたしたちは囲まれていた
誠の制服はまだ自分のそれと揃っていないから、余計に目立っていた
「誠くん、注目の的だね。みんなキャーキャー言ってる」
「そうかな、みんな普段と変わりないんじゃない?」
そんな風に言うから、わたしは回りをきょろきょろ見回す
気のせいだろうか…自分の病気のせいだろうか
こんな美青年と一緒に登校していて、女生徒達が何の反応もないわけがない
「俺、職員室に寄らないといけないから」
「職員室、どこか分かる?」
「案内してくれるの?」
もちろん、とわたしはうなずいた
「手を繋いでくれる?」
耳もとでささやかれた
わたしはふと顔を見上げると、爽やかな笑顔の誠が何食わぬ顔でいたのを見た
まさか職員室に手を繋いで行く男女はいないだろう
わたしの聞き間違いだと思ったその瞬間、手を握られてしまった
「迷子にならないように手を繋いでよ、イヤ?」
それには何も答えずに、私は手を振りほどいていた
「…だよね、兄貴との方がいいよね」
そんな寂しい声を背中で聞いて職員室へと誘導した
雨はまだ降り続いている
しとしとした氷雨は女々しくて鬱陶しい
まるで優柔不断で決断力に欠ける自分のようだ
だけど、どこか切なくて嫌いになれない
誠はわたしのクラスではなく、兄の特別進学クラスになった
普通に入学するのにも難しいこの学校に編入試験を受けて入って来たと知れ渡ってどよめきは絶えなかった
「生徒会長もかっこいいけど長谷川くんもピカイチだよね」
隣りの席のむつみが話しかけて来た
「そうかな」
「そういえば今朝、長谷川くんと一緒に登校してたよね?やっぱり転校生が来るって知ってたんだ」
「違うよ、知らなかった。たまたま会っただけで…」
「そうだよね、なずなかわいいもん。声かけられるよね…」
むつみの声は落胆していた
「だから違うって…」
励まそうとしたが無理みたいだった
むつみはむつみでとてもかわいい
そのことに本人は気づいてないみたいだ
休憩時間になり廊下に人だかりが出来ていると思ったら、誠の姿を見つけた
わたしは全く興味がなかったので次の授業の準備をしていたら、ついに見つかってしまったのか大きな声で呼ばれたのだ
「おーい、なずなちゃーん」
わたしは仕方なく声のする方へ笑いかけた
誠は掌を大きく振る
その大袈裟なリアクションが壺にはまったのかわたしもつられて手を振ってしまった
すると女子達の痛い視線を受けてしまう
それに気づかない誠は尚も手を振り続けている
「なずなちゃんのそばに行きたいんだけど、ちょっと無理みたいだから来てくれない?」
さらに痛い視線が突き刺さる
その視線を辿ると非常に不愉快で冷酷な面持ちのスバルがいた
わたしの笑顔は一瞬で氷結してしまい引きつったものになっただろう
わたしが誠のそばにいこうと席から離れ廊下を出ようとしたその瞬間、
何かに足がもつれてつまづきこけてしまった
周囲にいた女子達は冷ややかな笑い声をたてる
足がもつれた、というより誰かの足に引っ掛かってこけたような感じがした
慌てて近寄ってきたのは兄のスバルだった
「だいじょうぶか、」
すると誠も駆けつけてきた
「僕見たよ、なずなちゃん誰かの足に引っ掛かって転げたのを!」
「大丈夫だよ」
悔しい思いを必死に隠して笑顔でおどけてみせた
「偉い偉い、あとでご褒美あげなくちゃ」
わたしはその一言に目が見開き、固まってしまった
そんなわたしに気づきもしないで兄は頭を撫でている
「ちょっとこの場を離れようか」
そう言ったのは誠だった
誠はわたしと兄のやりとりを見逃さなかった
それから速やかに教室を離れ校舎の階段の踊り場に避難した
「なずな、今日転校してきた長谷川誠(はせがわまこと)くんだよ」
「知ってるよ」
「そうか…」
「まさのりの弟だもん」
「…やっぱりあいつの弟だったんだな」
兄の顔は一段と険しくなった
「休憩時間はなずなちゃんのお兄さんに校舎のなかを案内して貰うことになってるんだよ」
「そう……お兄、いや兄なら安心して頼れるよ。じゃあわたしはこれで」
「ちょっと待てよ」
そそくさに教室に帰ろうとした瞬間、兄が阻止した
「なずな、ご褒美忘れてないか?」
忘れていないわけではなかった
兄が思い出さないように、言い出さないようにしていたのだ
「そんなの、いらないから」
「照れるなよ、あいつの弟だからって意識してるんじゃないだろうな?」
「そんなわけないでしょ?」
わたしはすぐさま否定した
「だったら受けとれよ……」
「え!?」
力が怯んだその瞬間をつかれて兄のスバルの唇が重なる
「おい!なずなちゃん嫌がってるじゃないか」
そう言ってわたしの手首を引き寄せた
「嫌がってるどころか、石井におびえてるの分からないのか?」
兄の舌打ちは校舎に悲しく響いた
わたしは誠に助けて貰ってありがとうも言わず、二人の間をすり抜けてその場を去ってしまった
この作家の他の作品
表紙を見る
限られた時間、たった一度の出会い。
特別じゃないふたりの、特別な日常。
誰かと一緒に食事をすることは
誰かと一緒に生きることのように
大切な行為なのかもしれない。
中岡×なな
表紙を見る
熱い唇に冷たい手
言葉なんか忘れさせて
強いお酒に怖い夢
目を閉じたまま踊らせて
優しいジーンズに優しい瞳
懐かしい名前で呼んで
明るい場所へ続く道が
明るいとは限らない
出口はどこだ 入り口ばっかり
小さな庭に突入した
start*2018.7.20~
end* no data.
表紙を見る
あたまはまつぼっくり
体は枯れ枝
木の葉をきた“このはこぞう”は
山をあらしにくる人間を見はっています
ところがある日……、
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…