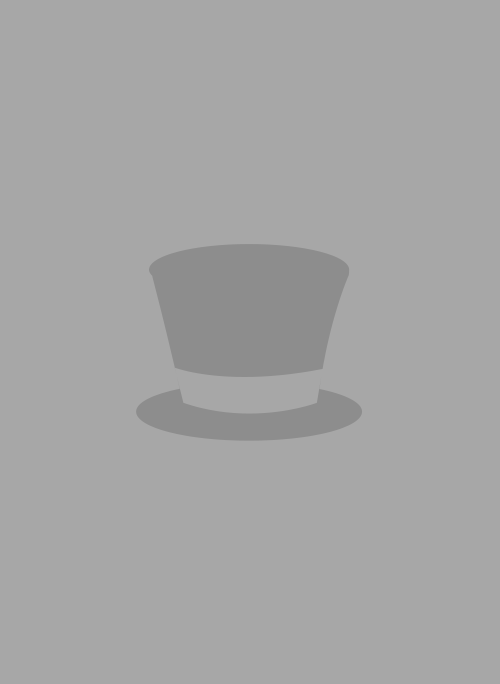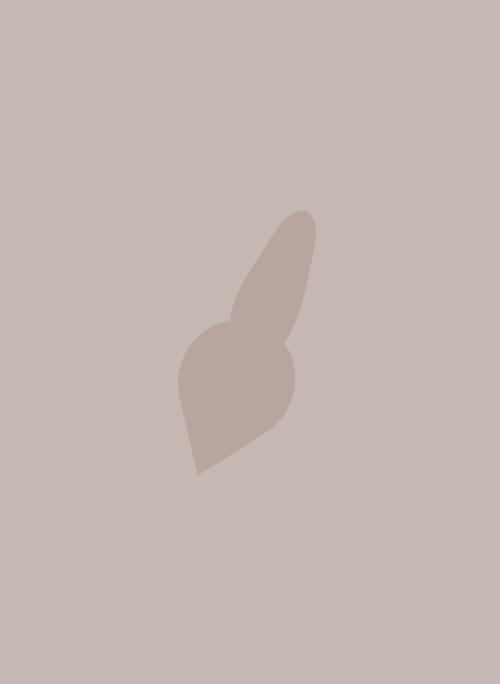ガラリと引き戸が開き、真っ先に飛び込んできたのは白い塊――もとい、タオルの山だった。
さっきの声の主らしいその女性は、からんころん、と、小気味よい音を伴って駆け寄る。
「大丈夫じゃないですよね……ごめんなさい」
彼女はそう言いながら、タオルを手渡してくれた。
ホテルに置いてあるような大判のバスタオル。僕はそれを頭から被り、髪を拭き、顔を拭き、肩を拭いた。
「ほんとに、ごめんなさい」
もう一枚あったタオルで、彼女は胸を拭いてくれた。
タオルに埋もれていてわからなかったけれど、彼女は少女のようだ。
華奢な身体。折れそうなくらい細い四肢に腰、けれど全身の均衡は取れていて。生成色のワンピースがよく似合っている。
黒とも灰とも言えない濃い鈍色の髪は、まっすぐに長く伸びている。ぱっちりとした大きな瞳にくるんと上を向いた睫毛……化粧っ気のない顔は、とてもかわいらしい。
……ん?
この子、どこかで――――……。
「……あの……?」
小首を傾げて僕を見上げる少女。なんども瞬きをする仕草もかわいい。
あ。もしかして、
「NANAさん……ですか?」
彼女はびっくりしたらしく、大きな瞳を更に大きくして、何回か瞬きを繰り返す。その間も、彼女は視線を外さない。
「はい、NANAです」
彼女はにっこりと笑んだ。
――20070702 / つづく
小首を傾げて僕を見上げる少女。なんども瞬きをする仕草もかわいい。
あ。もしかして、
「NANAさん……ですか?」
彼女はびっくりしたらしく、大きな瞳を更に大きくして、何回か瞬きを繰り返す。その間も、彼女は視線を外さない。
「はい、NANAです」
彼女はにっこりと笑んだ。
――20070702 / つづく
止まっていた時計の針が、動き出した
ゆっくりと静かに、けれど確実に……
彼は、落ち着かない様子で辺り――あたしの部屋をきょろきょろと見ていた。もしかしたら女の子の部屋自体、彼にしてみれば珍しいのかもしれない。
あの時、あたしは窓辺の鉢植えに水やりをしていた。
その途中、手が滑って――じょうろの落下は免(まぬが)れたけれど、中に入っていた水を通行人である彼にぶちまけてしまった。おかげで彼はびしょ濡れ。申し訳ないことをしてしまったと、彼を横目に小さな溜め息を吐いた。
ついさっきの出来事を思い出して、あたしはふっと笑った。ちょっと不謹慎かもしれないけれど。
なんとか掴んだじょうろを適当に机の上に置いて、あたしは部屋を飛び出した。
廊下の突き当たりにあるお風呂場から目についたタオルを抱えて、階段を駆け降りて。普段はあまり履かない下駄に足を突っ込んで、彼に駆け寄ったあたし。
あたしよりも頭ひとつ分背の高い彼は、とっても綺麗な目をしてた。
黒。
真っ黒。
吸い込まれそうな漆黒。
長い前髪から覗くその目にまっすぐ見つめられて、柄にもなく照れてしまう。あたしは目を反らして、彼の濡れた胸元を拭いた。
廊下の突き当たりにあるお風呂場から目についたタオルを抱えて、階段を駆け降りて。普段はあまり履かない下駄に足を突っ込んで、彼に駆け寄ったあたし。
あたしよりも頭ひとつ分背の高い彼は、とっても綺麗な目をしてた。
黒。
真っ黒。
吸い込まれそうな漆黒。
長い前髪から覗くその目にまっすぐ見つめられて、柄にもなく照れてしまう。あたしは目を反らして、彼の濡れた胸元を拭いた。
タオルにくるまった状態の彼を、あたしは躊躇(ためら)うことなく部屋へ上げた。
親元を離れて独り暮らしを満喫中だったから、誰かに気兼することもなかった。今思うと、見ず知らずの男の人を部屋に上げるなんてちょっと軽率だったけれど。
とりあえずあたしは、彼に着替えるよう勧めた。見たところ、男の人にしては肩幅も狭いみたいだし、レディースのLLなら着られなくなさそうだ。
ちょうどこのあいだ部屋着にと買ったTシャツが、そのサイズだった。あたしは戸口の脇に置いてあった籠の中からそのTシャツを取り出して、彼に手渡す。彼が着替る間、あたしは廊下で待つことにした。
引き戸を静かに締め、ふうと深く息を吐く。
……それにしても、さっきのは本当にびっくりした。
彼は、あたしをNANAだと言った。
NANAというのは、あたしの芸名だ。芸名といっても、タレントとか、そういうものではない。
あたしの親は、通信販売の会社・レイアーを経営している。レイアーが扱っているのはレディースのカットソーやスカート、アクセサリー。会社設立当時はティーンズをターゲットにしていたのだけれど、今ではハイティーンから20代前半の女性が主な購買層だ。
レイアー唯一のカタログ――“ЯeiaR(レイアー)”。
あたしは、ЯeiaRのモデルだった。
モデルといっても、通販カタログでしか活動していないから、あたし――NANAのことを知る人は、たぶんほとんどいない。しかも、最近は仕事もしていないし……ううん、そんなこと今はどうでもいい。
……彼は、何者なんだろう……?
――そういえば着替え、終わったかしら?
その時だった。
この作家の他の作品
表紙を見る
――二〇XX年。
度重なる不祥事に、
警視庁をはじめとする警察機構は
大幅な内部改革を行なった。
思考試験百問。
ヘキソミノテストとも呼ばれる、
人間を篩に掛ける検査。
犯罪傾向を持つ人間を徹底的に排除し、
選ばれた人間のみが
市民を守る警察官と成り得る。
そんな難関を突破し、
警察官となった青年が今、
入庁しようとしていた――。
since 6/1,2008
※ attention ※
流血など暴力的描写を含みます。
苦手な方はご注意ください。
また、メンタル要素を含みます。
心療中の方は特にご注意ください。
この物語はフィクションです。
表紙を見る
侵蝕スル、残酷ナ現実
悪夢ノ中デ アタシハ嘲笑ウ
-詩集-
In the World...
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…