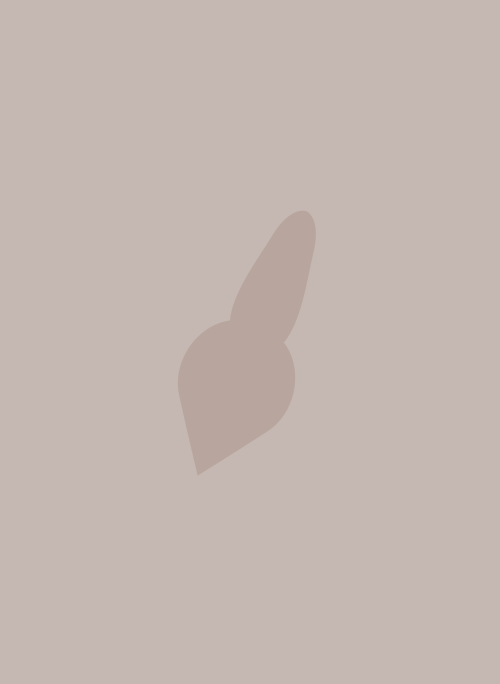「じゃぁあれだっ青羽ちゃんパパは青羽ちゃん産まれた時嬉しかっただろうねぇっ」
「…は…?」
津川さんのその突拍子も無い台詞を聞いた時思わず間抜けな声が口から洩れてしまった。
否だって私を産んだ制で母は死んだんだよ?どうして嬉しい?私を産まなければ母は死なずに済んだんだよ?
訳が分からず眉を潜めたままの私に津川さんは続けてこう言った。
「だってさっ大すきな奥さんから二人の間に産まれた子が大すきな奥さんにそっくりなわけだよ?ただでさえ嬉しいのにより一層嬉しくなるよっ」
分かってないなと思った。それで大すきな奥さんが死んじゃったわけだよ?
そう言うと津川さんははっとした顔をして慌てた後しゅんとなってしまった。
「やっでもでもやっぱ愛の結晶だからほら…っ!」
「あーもーはいはいはいはい黙んなりえ。」
ろくなことを言いそうにない津川さんの言葉を制する伊村さんの声が横から入った。
分かってないなと思った。
「…は…?」
津川さんのその突拍子も無い台詞を聞いた時思わず間抜けな声が口から洩れてしまった。
否だって私を産んだ制で母は死んだんだよ?どうして嬉しい?私を産まなければ母は死なずに済んだんだよ?
訳が分からず眉を潜めたままの私に津川さんは続けてこう言った。
「だってさっ大すきな奥さんから二人の間に産まれた子が大すきな奥さんにそっくりなわけだよ?ただでさえ嬉しいのにより一層嬉しくなるよっ」
分かってないなと思った。それで大すきな奥さんが死んじゃったわけだよ?
そう言うと津川さんははっとした顔をして慌てた後しゅんとなってしまった。
「やっでもでもやっぱ愛の結晶だからほら…っ!」
「あーもーはいはいはいはい黙んなりえ。」
ろくなことを言いそうにない津川さんの言葉を制する伊村さんの声が横から入った。
分かってないなと思った。
そう思ったはずなのに、どこかその言葉に救われた自分が居た。
もしかしたらずっと誰かにそう言って欲しかったのかも知れない。
産まれてきて良かったのだと。
望まれて産まれてきたのだと。
そう…思いたかったのかも知れない。
そう思わせて欲しかったのかも知れない。
甘えた考えだと我ながら思う。
「…馬鹿じゃないの」
自嘲気味に笑いながら津川さんの言葉にそう返した。
「青羽ちゃん…?」
頬に津川さんの温かい手の感触がした。
もしかしたらずっと誰かにそう言って欲しかったのかも知れない。
産まれてきて良かったのだと。
望まれて産まれてきたのだと。
そう…思いたかったのかも知れない。
そう思わせて欲しかったのかも知れない。
甘えた考えだと我ながら思う。
「…馬鹿じゃないの」
自嘲気味に笑いながら津川さんの言葉にそう返した。
「青羽ちゃん…?」
頬に津川さんの温かい手の感触がした。
「どうして泣いてるの…?」
ナイテル?
そう言われて数秒後、頬を伝う何か熱いものが何なのかを自覚した。
「…何でも…無い…。」
本当の馬鹿は私じゃなかろうか。
手で拭っても拭っても留まる所を知らないそれは、後から後から溢れつづけた。
それは数年分の感情だろうか。それとも自分の愚かさに対する悔しさだろうか。それとも…。
私は両手で顔を覆いしばらくの間泣き続けた。
肩を震わせ、しゃくり上げながら。
こんなに泣いたのは何年振りだろうか。しかも他人の前で。
伊村さんや名城くんなんてまともに話すのは今日が初めてなのに申し訳ないじゃないか。
そんな風に思いながらも後から後から溢れるそれを留めることは出来なくて
―すぐ隣に感じる津川さんの温度が暖かくて、心地良かった。
ナイテル?
そう言われて数秒後、頬を伝う何か熱いものが何なのかを自覚した。
「…何でも…無い…。」
本当の馬鹿は私じゃなかろうか。
手で拭っても拭っても留まる所を知らないそれは、後から後から溢れつづけた。
それは数年分の感情だろうか。それとも自分の愚かさに対する悔しさだろうか。それとも…。
私は両手で顔を覆いしばらくの間泣き続けた。
肩を震わせ、しゃくり上げながら。
こんなに泣いたのは何年振りだろうか。しかも他人の前で。
伊村さんや名城くんなんてまともに話すのは今日が初めてなのに申し訳ないじゃないか。
そんな風に思いながらも後から後から溢れるそれを留めることは出来なくて
―すぐ隣に感じる津川さんの温度が暖かくて、心地良かった。
「青羽ちゃんは部活もう決めた?」
教室移動の最中、津川さんがふと思い出したかのように尋ねてきた。
「…あー…多分入らない…面倒だし…」
どの部活に入っても人間関係はつきものだし、そんな面倒くさいの嫌。そう言葉を押し出すようにして言うと、津川さんは少し苦笑混じりに、でも少し嬉しそうに「そっか」とだけ答えた。
「…あんたは?」
「んっとねー陸上部かソフトボールかで迷ってるのー」
「運動部なのね…」
まぁ走るの早いしなぁなどとぼんやり考えながら歩く。すぐ横にはもう一つ分の足音がして。
桜の花も散り、深緑の季節。窓からふいてくる心地良い風に耳を澄ませていた。
教室移動の最中、津川さんがふと思い出したかのように尋ねてきた。
「…あー…多分入らない…面倒だし…」
どの部活に入っても人間関係はつきものだし、そんな面倒くさいの嫌。そう言葉を押し出すようにして言うと、津川さんは少し苦笑混じりに、でも少し嬉しそうに「そっか」とだけ答えた。
「…あんたは?」
「んっとねー陸上部かソフトボールかで迷ってるのー」
「運動部なのね…」
まぁ走るの早いしなぁなどとぼんやり考えながら歩く。すぐ横にはもう一つ分の足音がして。
桜の花も散り、深緑の季節。窓からふいてくる心地良い風に耳を澄ませていた。
「…裕芽と名城くんは何部入るの?」
あの日以来、私達四人は屋上で一緒にお弁当を食べるようになった。
「剣道部」
「俺も同じく」
ご飯が入ったままの口を手で覆いながらもごもご言わせ、裕芽が答えた。それに名城くんの声が続く。
「剣道部…」
袴…かっこいいなぁ等と考えを巡らせていると、横から声が割って入った。
「あのねあのねっ翔ちゃんの家道場なのっでねっ裕芽ちゃんも翔ちゃんも小1からずっと剣道やってるんだよー」
「へぇ…」
道場だなんて凄いのね。そう言うと名城くんは少し照れて赤くなりながらも嬉しそうにはにかんだ。
「…裕芽…女剣士…」
そうぼそりと呟くと、それが聞こえたのか裕芽がいきなりむせだした。
「ちょ…っあんったほんと突然突拍子もないこと言い出すわよねー!」
抱腹絶倒。
まさにそんな感じ。
そんな面白いこと言ったかしら…。
ぼんやりその光景を眺めていると、津川さんに横からつつかれた。
「ねーねー何で裕芽ちゃんは『裕芽』でわたしは『津川さん』なのー?」
不満気に見上げながらそう尋ねてくる。
…あ…そう言えばそうだ…。特に深い意味は無かったのだけれど…。第一『伊村さん』って言いにくいのよね。
「わたしも『りえ』が良い!」
と私が返事を返すより先に津川さんからの言葉があった。
まさにそんな感じ。
そんな面白いこと言ったかしら…。
ぼんやりその光景を眺めていると、津川さんに横からつつかれた。
「ねーねー何で裕芽ちゃんは『裕芽』でわたしは『津川さん』なのー?」
不満気に見上げながらそう尋ねてくる。
…あ…そう言えばそうだ…。特に深い意味は無かったのだけれど…。第一『伊村さん』って言いにくいのよね。
「わたしも『りえ』が良い!」
と私が返事を返すより先に津川さんからの言葉があった。
突然の津川さんの言葉に正直驚いた。
『りえ』
口に出してみようかと心の中で唱えて、口をつぐんだ。
「嫌。」
「ええええぇぇーなんでえぇー!!!」
私の返事に全身で抵抗する津川さん。『やだよー』と言って駄々をこねる姿はまるでお菓子を買ってもらえない小さい子のようである。
「別に『津川さん』で苦労してないから良い。」
そうはっきりと言うと津川さんの嘆きはより一層酷いものとなり、最終的には裕芽に怒られて大人しくなった。
が、私を見る目は未だ何かを訴えているようだ。
『りえ』
口に出してみようかと心の中で唱えて、口をつぐんだ。
「嫌。」
「ええええぇぇーなんでえぇー!!!」
私の返事に全身で抵抗する津川さん。『やだよー』と言って駄々をこねる姿はまるでお菓子を買ってもらえない小さい子のようである。
「別に『津川さん』で苦労してないから良い。」
そうはっきりと言うと津川さんの嘆きはより一層酷いものとなり、最終的には裕芽に怒られて大人しくなった。
が、私を見る目は未だ何かを訴えているようだ。
『りえ』って呼んでみようかな、って思った。
呼んでみたいなって。
でもどうしてもそう出来ない自分が居た。
恥ずかしくて
嬉しいけどでも
くすぐったくて。
慣れないこの喜びを人に見せるのは恥ずかしいから、バレないようにと必死に隠した。
こんな喜びを与えてくれた人だから、だから大切にしたいと思うけれど、本当にこの場所に私が相応しい人間かどうか自信がないからまだ呼べないなって思った。
だからまだしばらくは―…
「あれーっ青羽ちゃんー?」
帰り支度を済ませ、階段を下りている途中で誰かから声をかけられた。
声のした方へと目を向けると…
「…名城くん」
手にモップを持ったまま階段を一段飛ばしで下りてくる。
「今帰りー?」
いつもの笑顔でそう尋ねてくる。
私はそれに頷いた。
帰り支度を済ませ、階段を下りている途中で誰かから声をかけられた。
声のした方へと目を向けると…
「…名城くん」
手にモップを持ったまま階段を一段飛ばしで下りてくる。
「今帰りー?」
いつもの笑顔でそう尋ねてくる。
私はそれに頷いた。
この作品のキーワード
設定されていません
この作家の他の作品
表紙を見る
つらつらと
続く言ノ葉 繋がる言ノ葉
ひらひらと
それは舞って
折り重なって
そして いつかの
道の、果てへ
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…