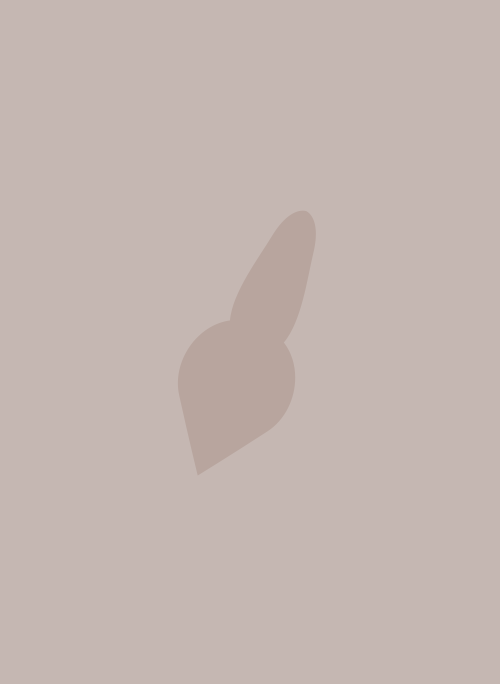何故だかそんな風に思い切り否定する人の言葉より、居心地がよく感じた。
「青羽ちゃーん次理科室だってー実験だよーぅ」
休み時間の度に津川さんは話し掛けてくる。移動教室の時は一緒に行こう、と言いながら。
私はと言うと大体何も言わずに立ち上がってその場から離れる。
それでも津川さんは話し掛けてくる。追い掛けてくる。―へこたれもせずに。
前を歩く私の後ろに微かな上靴の音がする。欝陶しいとも、津川さんが他の子達から顰蹙(ヒンシュク)をかうのではという不安もあった。でもやっぱり…少しだけ、少しだけ。
嬉しくて、くすぐったかった。
「青羽ちゃんっあのね!わたし青羽ちゃんに会って欲しい人が居るのっ」
津川さんの唐突な発言に思わず箸で掴んでいた唐揚げを落とした。
―お昼休み。津川さんと私はいつの間にかお昼を一緒に食べるようになっていた。…まぁ、席も隣だし…。
「…誰?」
「えーっとねーっ翔ちゃんと裕芽ちゃんっわたしが最初青羽ちゃんにぶつかった時に一緒に居た子なんだけど覚えてる?」
―覚えてる。
「…あの背の…高い子…?」
先程口へと運び損ねた唐揚げを掴む。
「そー!青羽ちゃん記憶力いいねぇっ」
そりゃね。あんたがあれだけ大騒ぎしてれば嫌でも覚えてますよ。
「でねっご飯食べたら会ってもらうからっ」
満面の笑みでそう告げる津川さん。そして私はまた唐揚げを落とした。
「…え…ちょ…ちょっと待って…え……今から…!?」
突然のことで理解が追いついていかない。
津川さんの唐突な発言に思わず箸で掴んでいた唐揚げを落とした。
―お昼休み。津川さんと私はいつの間にかお昼を一緒に食べるようになっていた。…まぁ、席も隣だし…。
「…誰?」
「えーっとねーっ翔ちゃんと裕芽ちゃんっわたしが最初青羽ちゃんにぶつかった時に一緒に居た子なんだけど覚えてる?」
―覚えてる。
「…あの背の…高い子…?」
先程口へと運び損ねた唐揚げを掴む。
「そー!青羽ちゃん記憶力いいねぇっ」
そりゃね。あんたがあれだけ大騒ぎしてれば嫌でも覚えてますよ。
「でねっご飯食べたら会ってもらうからっ」
満面の笑みでそう告げる津川さん。そして私はまた唐揚げを落とした。
「…え…ちょ…ちょっと待って…え……今から…!?」
突然のことで理解が追いついていかない。
「…ま…待って待っていきなりじゃ二人もびっくりするんじゃ…」
「びっくりしないよーぉだって昨日言っておいたもんっ」
びっくりするんじゃないのか、と言いかけた私の言葉を制して津川さんがそう答えた。
……何で私には昨日言ってくれなかったのよ。
そう思いつつため息をついて、唐揚げを今度こそ口に入れた。そんな私の様子を津川さんはにこにこしながら見てくる。
―腹をくくるしか無いか。
初対面の人と話すの苦手なのに…まぁ一対一じゃないだけマシか。
そう自分に無理矢理言い聞かせ、唐揚げをお茶で流し込んだ。
「びっくりしないよーぉだって昨日言っておいたもんっ」
びっくりするんじゃないのか、と言いかけた私の言葉を制して津川さんがそう答えた。
……何で私には昨日言ってくれなかったのよ。
そう思いつつため息をついて、唐揚げを今度こそ口に入れた。そんな私の様子を津川さんはにこにこしながら見てくる。
―腹をくくるしか無いか。
初対面の人と話すの苦手なのに…まぁ一対一じゃないだけマシか。
そう自分に無理矢理言い聞かせ、唐揚げをお茶で流し込んだ。
「おーりえ来た来たー」
津川さんに手を引かれるがままに歩いてたどり着いた先は屋上。不気味な音がする建て付けの悪いドアを開けるとそこには一面の青が広がっていた。
今日は天気がいいなぁなんてぼうっと考えていると、奥の方に座っている伊村さんが手を振りながら津川さんを呼んだ。
その対面に胡座をかいて座っている名城くんと目が合ったので、軽く会釈をすると緩い笑顔を返してくれた。
「わーい裕芽ちゃーんっ」
ぶんぶん手を振り返す津川さん。
元気だなと思う。
「行こっ青羽ちゃんっ」
そう言って差し延べられた手がほんの少し嬉しくてくすぐったくて。
短く返事をして差し延べられた手に軽く触れる。
「えっ!釧路さんて直兄の妹なの!!?」
伊村さんの動揺の色を含んだ大きな声が屋上中に響き渡った。
「わたしもこの間びっくりしちゃったーぁ」
話題はこの間私がお兄のバイト先(津川さんのお父さんが経営しているケーキ屋)に忘れ物を届けに行った時の話になっていた。
―確かに私もあの時は驚いた。…世間は狭いのだなぁと…。
「あ―…言われてみれば似て………ないねぇ」
苦笑気味に名城くんが言う。
うん、私もそう思う。
「…お兄は…父親似で…私は…母親似らしいから…。」
『らしい』。
実際の母を見たことは無いからそうとしか言えない。ただ母の生前の写真を見る限り顔自体は似ている部類に入るとは思う。尤も彼女の方が幾分か明るそうだが。
「じゃぁあれだっ青羽ちゃんパパは青羽ちゃん産まれた時嬉しかっただろうねぇっ」
「…は…?」
津川さんのその突拍子も無い台詞を聞いた時思わず間抜けな声が口から洩れてしまった。
否だって私を産んだ制で母は死んだんだよ?どうして嬉しい?私を産まなければ母は死なずに済んだんだよ?
訳が分からず眉を潜めたままの私に津川さんは続けてこう言った。
「だってさっ大すきな奥さんから二人の間に産まれた子が大すきな奥さんにそっくりなわけだよ?ただでさえ嬉しいのにより一層嬉しくなるよっ」
分かってないなと思った。それで大すきな奥さんが死んじゃったわけだよ?
そう言うと津川さんははっとした顔をして慌てた後しゅんとなってしまった。
「やっでもでもやっぱ愛の結晶だからほら…っ!」
「あーもーはいはいはいはい黙んなりえ。」
ろくなことを言いそうにない津川さんの言葉を制する伊村さんの声が横から入った。
分かってないなと思った。
「…は…?」
津川さんのその突拍子も無い台詞を聞いた時思わず間抜けな声が口から洩れてしまった。
否だって私を産んだ制で母は死んだんだよ?どうして嬉しい?私を産まなければ母は死なずに済んだんだよ?
訳が分からず眉を潜めたままの私に津川さんは続けてこう言った。
「だってさっ大すきな奥さんから二人の間に産まれた子が大すきな奥さんにそっくりなわけだよ?ただでさえ嬉しいのにより一層嬉しくなるよっ」
分かってないなと思った。それで大すきな奥さんが死んじゃったわけだよ?
そう言うと津川さんははっとした顔をして慌てた後しゅんとなってしまった。
「やっでもでもやっぱ愛の結晶だからほら…っ!」
「あーもーはいはいはいはい黙んなりえ。」
ろくなことを言いそうにない津川さんの言葉を制する伊村さんの声が横から入った。
分かってないなと思った。
そう思ったはずなのに、どこかその言葉に救われた自分が居た。
もしかしたらずっと誰かにそう言って欲しかったのかも知れない。
産まれてきて良かったのだと。
望まれて産まれてきたのだと。
そう…思いたかったのかも知れない。
そう思わせて欲しかったのかも知れない。
甘えた考えだと我ながら思う。
「…馬鹿じゃないの」
自嘲気味に笑いながら津川さんの言葉にそう返した。
「青羽ちゃん…?」
頬に津川さんの温かい手の感触がした。
もしかしたらずっと誰かにそう言って欲しかったのかも知れない。
産まれてきて良かったのだと。
望まれて産まれてきたのだと。
そう…思いたかったのかも知れない。
そう思わせて欲しかったのかも知れない。
甘えた考えだと我ながら思う。
「…馬鹿じゃないの」
自嘲気味に笑いながら津川さんの言葉にそう返した。
「青羽ちゃん…?」
頬に津川さんの温かい手の感触がした。
「どうして泣いてるの…?」
ナイテル?
そう言われて数秒後、頬を伝う何か熱いものが何なのかを自覚した。
「…何でも…無い…。」
本当の馬鹿は私じゃなかろうか。
手で拭っても拭っても留まる所を知らないそれは、後から後から溢れつづけた。
それは数年分の感情だろうか。それとも自分の愚かさに対する悔しさだろうか。それとも…。
私は両手で顔を覆いしばらくの間泣き続けた。
肩を震わせ、しゃくり上げながら。
こんなに泣いたのは何年振りだろうか。しかも他人の前で。
伊村さんや名城くんなんてまともに話すのは今日が初めてなのに申し訳ないじゃないか。
そんな風に思いながらも後から後から溢れるそれを留めることは出来なくて
―すぐ隣に感じる津川さんの温度が暖かくて、心地良かった。
ナイテル?
そう言われて数秒後、頬を伝う何か熱いものが何なのかを自覚した。
「…何でも…無い…。」
本当の馬鹿は私じゃなかろうか。
手で拭っても拭っても留まる所を知らないそれは、後から後から溢れつづけた。
それは数年分の感情だろうか。それとも自分の愚かさに対する悔しさだろうか。それとも…。
私は両手で顔を覆いしばらくの間泣き続けた。
肩を震わせ、しゃくり上げながら。
こんなに泣いたのは何年振りだろうか。しかも他人の前で。
伊村さんや名城くんなんてまともに話すのは今日が初めてなのに申し訳ないじゃないか。
そんな風に思いながらも後から後から溢れるそれを留めることは出来なくて
―すぐ隣に感じる津川さんの温度が暖かくて、心地良かった。
この作品のキーワード
設定されていません
この作家の他の作品
表紙を見る
つらつらと
続く言ノ葉 繋がる言ノ葉
ひらひらと
それは舞って
折り重なって
そして いつかの
道の、果てへ
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…