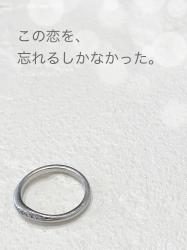「…。」
「無理しなくていいよ。」
上手く話せなくて、上手く…動けない。
そんなあたしの状態を知ってか知らないでか、コータローは決してあたしを急かさない。
シャラ……シャラ…
ただ、うつむいていても、コータローが近づいてきていることは、心地よいコータローの音がだんだん大きくなることでわかる。
「…清田さん。」
「コータロ……。」
それ以上、言えなかった……名前を呼ばれた瞬間、あたしはコータローの腕の中にいた。
「ごめん…。何か、泣いてるの見たら、こうしたくなった。」
あたしはうんと頷いてから、コータローの胸のあたりにおでこを付けた。
雨が、急に激しく降り出したけど、コータローの心臓の音が、少しずつあたしを落ち着かせていった。
コータローはしばらくこのままでいてくれて、あたしは良くわからない気持ちのまま泣きやんで、小降りにはなったけどまだ止まない雨の中を、コータローと歩いた。
ゆうちゃんが今日は日直で、担任の手伝いをしていたことなど知りもしなかったあたしは、コータローとの一部始終を見られていたなんて、気付きもしなかった…。
「無理しなくていいよ。」
上手く話せなくて、上手く…動けない。
そんなあたしの状態を知ってか知らないでか、コータローは決してあたしを急かさない。
シャラ……シャラ…
ただ、うつむいていても、コータローが近づいてきていることは、心地よいコータローの音がだんだん大きくなることでわかる。
「…清田さん。」
「コータロ……。」
それ以上、言えなかった……名前を呼ばれた瞬間、あたしはコータローの腕の中にいた。
「ごめん…。何か、泣いてるの見たら、こうしたくなった。」
あたしはうんと頷いてから、コータローの胸のあたりにおでこを付けた。
雨が、急に激しく降り出したけど、コータローの心臓の音が、少しずつあたしを落ち着かせていった。
コータローはしばらくこのままでいてくれて、あたしは良くわからない気持ちのまま泣きやんで、小降りにはなったけどまだ止まない雨の中を、コータローと歩いた。
ゆうちゃんが今日は日直で、担任の手伝いをしていたことなど知りもしなかったあたしは、コータローとの一部始終を見られていたなんて、気付きもしなかった…。