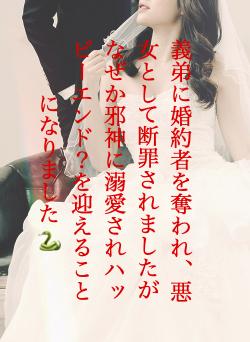レレナとミレイの言葉に集中した為、スカーレットは縫い針で指を刺してしまった。此れで七回目だ。
「姉さん、大丈夫?」
ジェイドは直ぐにスカーレットの指にテープを貼った。スカーレットが指を刺してばかりいるので衣装づくりが全く進まなかった。
「こういうのは、いつもジェイドがしているから」
「ジェイド。アンタ、姉さんを甘やかしすぎなんじゃないの?」
「たった一人の僕の姉さんなんだから当然です」
「はいはい」
ミレイはシスコン丸出しのジェイドに呆れて、此れ以上は突っ込まないことにした。
「ジェイドさんはモテるんじゃないですか?お姉さん思いだから女性に優しいってことが分かりますし、手先が器用でお裁縫もできるのでポイント高いですよね」
話が変な方向になったなと、ジェイドは思った。
「告白されたことは今まで一度もありませんよ」
こういう手合いの話題は苦手なので早々に終わりにしたいので牽制の意味も込めて言ったのだが、恋バナが大好きな女性には通じなかった。
「其れってジェイドの周りの女が見る目がなかったってこと?若しくはジェイドの嘘ね」
「嘘って・・・・」
「どうなの、スカーレット?」
ミレイは埒が明かないので、答えをジェイド本人ではなく、スカーレットに求めた。
「私もそんな場面、見たことがないですね」
「原因はシスコンだからじゃないですか?」
「きっと其のせいね」
「会長達、実は結構暇でしょう」
「僕達を使って遊んでますもんね」
スカーレットとジェイドはジト目で二人を見た。ミレイとレレナは空気が重苦しくなってきたので「さぁて仕事、仕事」と言ってスカーレットとジェイドから目を逸らした。
スカーレットも早く仕事を終わらせたいので此れ以上、深く突っ込むことはしなかった。手に持っている布に針を刺した。
「いったぁー」
そして、またもや自分の指を刺した。此れで八回目。
夜。体育館を静寂と闇が包む。唯一、過酷な現実から目を閉じることを許される時間だ。もしかしたら一日で一番、幸せな時間なのかもしれない。
「姉さん、まだ起きてる?」
「姉さん、大丈夫?」
ジェイドは直ぐにスカーレットの指にテープを貼った。スカーレットが指を刺してばかりいるので衣装づくりが全く進まなかった。
「こういうのは、いつもジェイドがしているから」
「ジェイド。アンタ、姉さんを甘やかしすぎなんじゃないの?」
「たった一人の僕の姉さんなんだから当然です」
「はいはい」
ミレイはシスコン丸出しのジェイドに呆れて、此れ以上は突っ込まないことにした。
「ジェイドさんはモテるんじゃないですか?お姉さん思いだから女性に優しいってことが分かりますし、手先が器用でお裁縫もできるのでポイント高いですよね」
話が変な方向になったなと、ジェイドは思った。
「告白されたことは今まで一度もありませんよ」
こういう手合いの話題は苦手なので早々に終わりにしたいので牽制の意味も込めて言ったのだが、恋バナが大好きな女性には通じなかった。
「其れってジェイドの周りの女が見る目がなかったってこと?若しくはジェイドの嘘ね」
「嘘って・・・・」
「どうなの、スカーレット?」
ミレイは埒が明かないので、答えをジェイド本人ではなく、スカーレットに求めた。
「私もそんな場面、見たことがないですね」
「原因はシスコンだからじゃないですか?」
「きっと其のせいね」
「会長達、実は結構暇でしょう」
「僕達を使って遊んでますもんね」
スカーレットとジェイドはジト目で二人を見た。ミレイとレレナは空気が重苦しくなってきたので「さぁて仕事、仕事」と言ってスカーレットとジェイドから目を逸らした。
スカーレットも早く仕事を終わらせたいので此れ以上、深く突っ込むことはしなかった。手に持っている布に針を刺した。
「いったぁー」
そして、またもや自分の指を刺した。此れで八回目。
夜。体育館を静寂と闇が包む。唯一、過酷な現実から目を閉じることを許される時間だ。もしかしたら一日で一番、幸せな時間なのかもしれない。
「姉さん、まだ起きてる?」