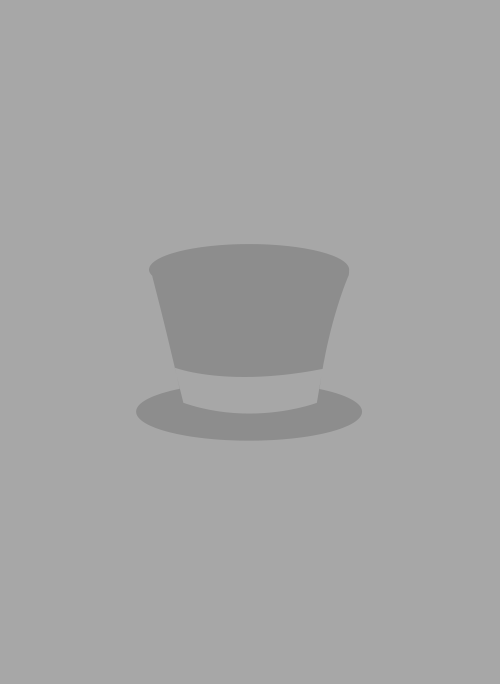「まあ…ゲストが、入らない店は…」
エイリは、ホール内のアイスボックスに、氷をいれながら、
(もう衰退していくって…ことだけどな)
エイリは、横目で店内を観察した。
ベテランや人気のホステスにつく太客。
確かにそれは、大切だが…年輩が多すぎる。
お客だって、何年ついても落ちないホステスに、いつまでも、金を貢ぐとは思えないし…
彼女と勘違いしたり、金を使うことで、自分の力を示しているじじいも…倒産したり、亡くなるかもしれない。
(少し…客層がおかしいか?)
年輩ばかりで、中間の少し若い20代後半から30代前半のお客がいない。
何人かいるが…ホステスを落とすのに躍起になっている男だけだ。
(これは…)
エイリは人に見られないように、にやりと、笑った。
(どこか近くに…いい店ができたか…)
この業界に安定などない。
お客は店につくより、女につく。いい店に、いい女がいれば、そこに移る。
ある意味、店や女に情を持って通うお客は、駄目だろう。
(所詮…訳ありが多い)
女は理由がある。
テレビドラマみたいな世界はない。
(所詮…男と女。ドラマじゃない)
エイリはホールを見回しながら、ほくそ笑んだ。
エイリは、ホール内のアイスボックスに、氷をいれながら、
(もう衰退していくって…ことだけどな)
エイリは、横目で店内を観察した。
ベテランや人気のホステスにつく太客。
確かにそれは、大切だが…年輩が多すぎる。
お客だって、何年ついても落ちないホステスに、いつまでも、金を貢ぐとは思えないし…
彼女と勘違いしたり、金を使うことで、自分の力を示しているじじいも…倒産したり、亡くなるかもしれない。
(少し…客層がおかしいか?)
年輩ばかりで、中間の少し若い20代後半から30代前半のお客がいない。
何人かいるが…ホステスを落とすのに躍起になっている男だけだ。
(これは…)
エイリは人に見られないように、にやりと、笑った。
(どこか近くに…いい店ができたか…)
この業界に安定などない。
お客は店につくより、女につく。いい店に、いい女がいれば、そこに移る。
ある意味、店や女に情を持って通うお客は、駄目だろう。
(所詮…訳ありが多い)
女は理由がある。
テレビドラマみたいな世界はない。
(所詮…男と女。ドラマじゃない)
エイリはホールを見回しながら、ほくそ笑んだ。