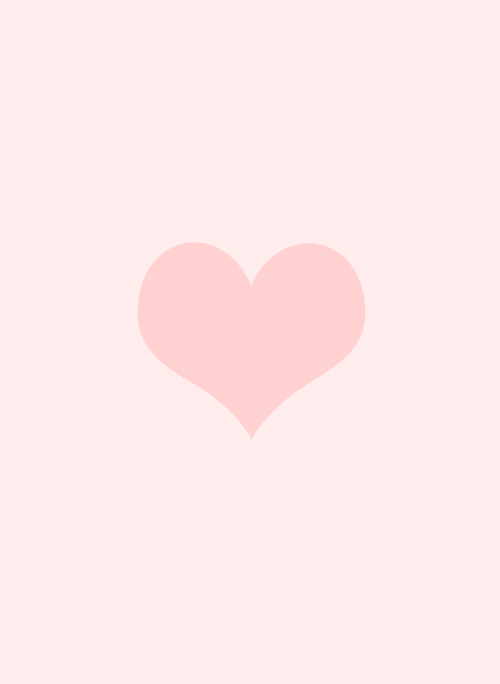私の前に立つとすっと手を振り上げる。
――――バチンッ!
私の左頬を思い切り殴った。周りに乾いた音が響いた。近くにいた人が莉音を止めに入る。私はその場に座り込んだ。莉音が私を殴ったことに気付いたのはこのときだ。私が莉音を見上げるとそこにいたのは目に涙をためてなくのを必死にこらえている莉音だった。
「……莉音?」
――――バチンッ!
私の左頬を思い切り殴った。周りに乾いた音が響いた。近くにいた人が莉音を止めに入る。私はその場に座り込んだ。莉音が私を殴ったことに気付いたのはこのときだ。私が莉音を見上げるとそこにいたのは目に涙をためてなくのを必死にこらえている莉音だった。
「……莉音?」
莉音は私をにらみつけると周りの人の手を振りほどいて私を無理やり立たせた。
「なんか言えばわかってくれるの?栞菜は、どうしてそんなに遠慮するの?迷惑だなんて思ってないって言ってるじゃんっ!!どうしてわかってくれないのっ!!お礼なんてほしくないのっ!私たちはただ栞菜に笑っていてほしいから……。だから自分たちで勝手に動いてるだけだよ……。だから迷惑だなんて、思ってほしくないよ……。お礼がしたいって思うなら、ずっと笑っていてよ……」
そういうと、莉音は私を抱きしめた。
「り、おん……ごめん、なさい……。私、外国に行っちゃう、でしょう……?だから、それまではずっと迷惑かけずに、笑顔でいようっておもってっ……それ、でねっ……」
私は泣き出してしまって上手に伝えられなかったけど、莉音は私を抱きしめたままうんうんと頷いていてくれた。私の肩が少しぬれていて、莉音が震えてる。
……莉音も泣いてるんだ。私が泣かせちゃった……。
「なんか言えばわかってくれるの?栞菜は、どうしてそんなに遠慮するの?迷惑だなんて思ってないって言ってるじゃんっ!!どうしてわかってくれないのっ!!お礼なんてほしくないのっ!私たちはただ栞菜に笑っていてほしいから……。だから自分たちで勝手に動いてるだけだよ……。だから迷惑だなんて、思ってほしくないよ……。お礼がしたいって思うなら、ずっと笑っていてよ……」
そういうと、莉音は私を抱きしめた。
「り、おん……ごめん、なさい……。私、外国に行っちゃう、でしょう……?だから、それまではずっと迷惑かけずに、笑顔でいようっておもってっ……それ、でねっ……」
私は泣き出してしまって上手に伝えられなかったけど、莉音は私を抱きしめたままうんうんと頷いていてくれた。私の肩が少しぬれていて、莉音が震えてる。
……莉音も泣いてるんだ。私が泣かせちゃった……。
「違うよ、バカッ!栞菜が私を泣かせたわけじゃないもんっ……。絶対、違うんだから……」
気付かれた。莉音には、私の考えてることなんてお見通しなんだ。
莉音は、私をきつく抱きしめた。私も、それに答えるように莉音をぎゅっと抱きしめた。すると周りから、パチパチと拍手の音が聞こえてきた。
私たちは周りがいることをすっかり忘れて抱き合っていたのに気付いて、急いで離れた。そして、二人でおかしくなって笑いあった。
「栞菜、私も宮野もね、見返りを求めているわけじゃないの。ただ三人で笑いあっていたいだけなんだよ」
笑いあいたい……。
「だから、迷惑かけてるわけでも、お礼を言われたいわけでもない。だって、半分は自分たちのために動いてるようなものなんだ。栞菜と、ずっと笑っていたいんだよ。だから、気にしないでほしい」
私は、莉音の言葉に大きく頷いた。
絶対、大丈夫だよ。笑顔でいられるよ。
気付かれた。莉音には、私の考えてることなんてお見通しなんだ。
莉音は、私をきつく抱きしめた。私も、それに答えるように莉音をぎゅっと抱きしめた。すると周りから、パチパチと拍手の音が聞こえてきた。
私たちは周りがいることをすっかり忘れて抱き合っていたのに気付いて、急いで離れた。そして、二人でおかしくなって笑いあった。
「栞菜、私も宮野もね、見返りを求めているわけじゃないの。ただ三人で笑いあっていたいだけなんだよ」
笑いあいたい……。
「だから、迷惑かけてるわけでも、お礼を言われたいわけでもない。だって、半分は自分たちのために動いてるようなものなんだ。栞菜と、ずっと笑っていたいんだよ。だから、気にしないでほしい」
私は、莉音の言葉に大きく頷いた。
絶対、大丈夫だよ。笑顔でいられるよ。
「莉音。私と約束してくれる?」
莉音は、軽く頷く。
「私は、どこに行ってもずっと笑ってられるようにする。だから、莉音はもっとありのままの自分でいて?」
莉音は、一瞬驚いて顔を伏せた。私は、莉音の頬に手を添えて顔を上げさせた。
「私と宮野以外の前だと、まだ自分を隠してるでしょう?せっかく心の優しい莉音のことに、それじゃぁ周りは気付いてくれないよ?」
優しい……?
「ね?私の最後のお願いだよ。ずっとずっと守ってほしい、最後のお願い。大丈夫。絶対、大丈夫だよ?」
私は、莉音に微笑んで「ゆびきり、しよ?」といった。
莉音は、ちょっと迷っていたけど笑顔でゆびきりをしてくれた。
その後、私たちは手をつないで教室に戻った。
莉音は、軽く頷く。
「私は、どこに行ってもずっと笑ってられるようにする。だから、莉音はもっとありのままの自分でいて?」
莉音は、一瞬驚いて顔を伏せた。私は、莉音の頬に手を添えて顔を上げさせた。
「私と宮野以外の前だと、まだ自分を隠してるでしょう?せっかく心の優しい莉音のことに、それじゃぁ周りは気付いてくれないよ?」
優しい……?
「ね?私の最後のお願いだよ。ずっとずっと守ってほしい、最後のお願い。大丈夫。絶対、大丈夫だよ?」
私は、莉音に微笑んで「ゆびきり、しよ?」といった。
莉音は、ちょっと迷っていたけど笑顔でゆびきりをしてくれた。
その後、私たちは手をつないで教室に戻った。
「Episode7」
それから、二か月が過ぎた。宮野には相変わらず何もできなかったけど、笑顔で送り出すと言ってくれた。莉音も笑っている顔を覚えていてほしいと言って笑顔だ。
ふたりへのサプライズは何とか成功。二人とも笑ってくれて、楽しい一日を過ごすことができた。そしたら翌日は、クラス全員がお別れ会を開いてくれた。嬉しくて嬉しくて涙が止まらなかった。それをみんなが嬉しそうに見ていた。
嬉し涙が止まらなかった私を見て、みんなは優しく笑ってみていてくれた。その雰囲気が優しくて嬉しくて、私があんなに嫌いだった学校が好きになったんだ。最後にみんなの優しさに触れることができて、すごく嬉しかった。みんなは、こんなにもあたたかい人だったんだ。
そして今日、私はママのところへ行く。みんなは先生に頼んで私が行くまでの間だけ学校を休ませてもらったそうだ。そこまでしてくれるクラスメイトを一時期でも怨んでいたことを後悔した。
でも、最後にこうやってみんなが笑顔で送り出してくれたんだ。莉音や宮野もいる。みんなが笑顔でいるんだ、私を送り出すために。
私は、精一杯の笑顔をみんなに向けてみんなに別れを告げた。
ふたりへのサプライズは何とか成功。二人とも笑ってくれて、楽しい一日を過ごすことができた。そしたら翌日は、クラス全員がお別れ会を開いてくれた。嬉しくて嬉しくて涙が止まらなかった。それをみんなが嬉しそうに見ていた。
嬉し涙が止まらなかった私を見て、みんなは優しく笑ってみていてくれた。その雰囲気が優しくて嬉しくて、私があんなに嫌いだった学校が好きになったんだ。最後にみんなの優しさに触れることができて、すごく嬉しかった。みんなは、こんなにもあたたかい人だったんだ。
そして今日、私はママのところへ行く。みんなは先生に頼んで私が行くまでの間だけ学校を休ませてもらったそうだ。そこまでしてくれるクラスメイトを一時期でも怨んでいたことを後悔した。
でも、最後にこうやってみんなが笑顔で送り出してくれたんだ。莉音や宮野もいる。みんなが笑顔でいるんだ、私を送り出すために。
私は、精一杯の笑顔をみんなに向けてみんなに別れを告げた。
「……着いた」
ママはどこだろう。このあたりで待ち合わせなはずだけど……。
「ちょっとっ!やめなさいよっ!」
あっ!見つけた。なんか男の人に絡まれてるし……。はぁ、ママってば。自分が可愛すぎるって自覚ないんだから。全く、もぉ……。
私はママの方へ走ると、その男の足を薙ぎ払った。
「ママから離れて」
すると男はむくっと立ち上がって、私を睨んだ。
「嬢ちゃん。邪魔するなら、容赦しねぇぞ」
うるっさいなぁ……面倒だ、さっさと倒してしまおうか。
「やれば?私、強いもの。じゃぁ、おさきにっ」
そういって、私は男の腹を殴った。男は蹲ってもがいてる。だから言ったのに。私強いって。
ママはどこだろう。このあたりで待ち合わせなはずだけど……。
「ちょっとっ!やめなさいよっ!」
あっ!見つけた。なんか男の人に絡まれてるし……。はぁ、ママってば。自分が可愛すぎるって自覚ないんだから。全く、もぉ……。
私はママの方へ走ると、その男の足を薙ぎ払った。
「ママから離れて」
すると男はむくっと立ち上がって、私を睨んだ。
「嬢ちゃん。邪魔するなら、容赦しねぇぞ」
うるっさいなぁ……面倒だ、さっさと倒してしまおうか。
「やれば?私、強いもの。じゃぁ、おさきにっ」
そういって、私は男の腹を殴った。男は蹲ってもがいてる。だから言ったのに。私強いって。
その男は、私を見て怯えたまま一目散に逃げていった。私は軽く手を払うと、ママのほうを向いた。
「……ママ。ママ可愛いんだから、一人でうろついてちゃダメじゃんっ!心配したんだよ?ママは格闘技ができるわけじゃないんだから。にしても、さっきの人は日本語しゃべれるんだね」
するとママはごめんねと言って立ちあがた。
「ここは空港だからよ。日本人だっているわ。ガラの悪いのもいるけどね。まぁ、空港を出たら、ほとんど英語の人ばっかりだから。気を付けてね」
ママは私の手を引いて、歩き出した。ママの言った通り、空港を出れば英語ばっかりが飛び交っていた。まぁ、言ってることはわかるんだけどね。勉強したし。英検二級まではとったし。ママには内緒でだけどね。
「栞菜、ちょっとママごはん買ってくるから、そこで待っててくれる?ベンチが近くにあるから、そこで座ってて?」
そう言ってベンチを指さして店の方へと去って行ってしまった。
「……ママ。ママ可愛いんだから、一人でうろついてちゃダメじゃんっ!心配したんだよ?ママは格闘技ができるわけじゃないんだから。にしても、さっきの人は日本語しゃべれるんだね」
するとママはごめんねと言って立ちあがた。
「ここは空港だからよ。日本人だっているわ。ガラの悪いのもいるけどね。まぁ、空港を出たら、ほとんど英語の人ばっかりだから。気を付けてね」
ママは私の手を引いて、歩き出した。ママの言った通り、空港を出れば英語ばっかりが飛び交っていた。まぁ、言ってることはわかるんだけどね。勉強したし。英検二級まではとったし。ママには内緒でだけどね。
「栞菜、ちょっとママごはん買ってくるから、そこで待っててくれる?ベンチが近くにあるから、そこで座ってて?」
そう言ってベンチを指さして店の方へと去って行ってしまった。
「え、ちょっとママっ!……まぁ、いっか。戻ってくるまで待ってよう。ちょっと心配だけどね」
変わってなかった。私がおぼえていたママと。まぁ、ちょっと老けてたけど。でも、あの優しさも笑顔も、私の幼い記憶と全く同じだった。どうして信じなかったのだろう。
……信じなかったんじゃない。
信じようとしなかったんだ。周りを。自分を。
でも、もう信じることの大切さを知ったから。教えくれたから。二人が教えてくれたから。私は、人を信じる。心から信じられる関係を築いていくんだ。人が大好きになれたから。もう、迷わないよ。二人を信じて頑張ってくよ。二人がくれた言葉を信じて、元気にやっていくから。
「……絶対、大丈夫だよ」
変わってなかった。私がおぼえていたママと。まぁ、ちょっと老けてたけど。でも、あの優しさも笑顔も、私の幼い記憶と全く同じだった。どうして信じなかったのだろう。
……信じなかったんじゃない。
信じようとしなかったんだ。周りを。自分を。
でも、もう信じることの大切さを知ったから。教えくれたから。二人が教えてくれたから。私は、人を信じる。心から信じられる関係を築いていくんだ。人が大好きになれたから。もう、迷わないよ。二人を信じて頑張ってくよ。二人がくれた言葉を信じて、元気にやっていくから。
「……絶対、大丈夫だよ」
この作家の他の作品
表紙を見る
まだ一度も本気で異性を愛したことがない
澤田 恵里菜(サワダ エリナ)
優しいけどどこか幼いテニス少年
山内 悠介(ヤマウチ ユウスケ)
誰かを本気で好きになることなんてないって思ってた
これが本気ってやつなの?
じゃあ、なんでこんなことしちゃうの……?
自分の本当の気持ちがわからないまま時を重ねていく。
やっとわかった時には、もう遅いんだ
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…