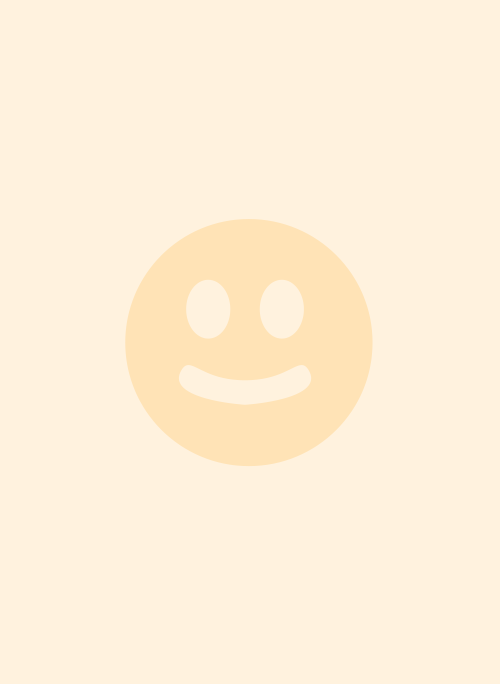そもそも、戦に正義などは有り得ない。
『正しい戦争』などこの世には存在しない。
あるのは両者の戦いを起こす大義名分のみ。
どちらもそれを正義と信じて戦っているだけだ。
だがどんな大義をかざしても、人を殺めていい正義など存在しない。
許される人殺しなどないのだ。
相手が敵であっても、罪人であっても、人の命を奪ったという事実が重くのしかかるのがその証拠。
命を奪うという事は、それだけで罪なのだ。
「しかし乙女。小国は…お前の国は侵略戦争を仕掛けられたのだ。それに対し、抵抗をするのは当然だと思わぬか?白旗を上げて植民地然とした扱いを受ける事が、お前の考える正しい選択か?」
「それは違う。侵略に屈する事は正しい判断ではない。だが…」
その為に敵兵を殺めていては、侵略者と同じなのではないか。
乙女の途切れた言葉には、そんな思いが込められていた。
「…せめて私は、理想に殉じる事で、その罪の意識から逃れようとしていただけなのかもしれない…騎士道、誇り、矜持…常々口にしてきた言葉だが…」
彼女は自嘲気味に笑った。
「ただの逃げ口上だと、獅子王に言われたような気がした。私が言っているのは、人殺しを兵士達に肯定させ、己の罪を誤魔化し、綺麗事を並べて彼らを自由に操りたいだけの…」
「もうやめろ」
俺は乙女の言葉を遮った。
「お前らしくもない。信念を曲げるなど」
『正しい戦争』などこの世には存在しない。
あるのは両者の戦いを起こす大義名分のみ。
どちらもそれを正義と信じて戦っているだけだ。
だがどんな大義をかざしても、人を殺めていい正義など存在しない。
許される人殺しなどないのだ。
相手が敵であっても、罪人であっても、人の命を奪ったという事実が重くのしかかるのがその証拠。
命を奪うという事は、それだけで罪なのだ。
「しかし乙女。小国は…お前の国は侵略戦争を仕掛けられたのだ。それに対し、抵抗をするのは当然だと思わぬか?白旗を上げて植民地然とした扱いを受ける事が、お前の考える正しい選択か?」
「それは違う。侵略に屈する事は正しい判断ではない。だが…」
その為に敵兵を殺めていては、侵略者と同じなのではないか。
乙女の途切れた言葉には、そんな思いが込められていた。
「…せめて私は、理想に殉じる事で、その罪の意識から逃れようとしていただけなのかもしれない…騎士道、誇り、矜持…常々口にしてきた言葉だが…」
彼女は自嘲気味に笑った。
「ただの逃げ口上だと、獅子王に言われたような気がした。私が言っているのは、人殺しを兵士達に肯定させ、己の罪を誤魔化し、綺麗事を並べて彼らを自由に操りたいだけの…」
「もうやめろ」
俺は乙女の言葉を遮った。
「お前らしくもない。信念を曲げるなど」
…乙女は首を横に振った。
「悪かった。ただの独り言だ、忘れてくれ」
気持ちを切り替えるように一つ大きく息を吐いて、乙女は表情を引き締めた。
「後日、獅子の国に向かおうと思う」
「獅子王のところへか?」
俺の言葉に乙女は頷いた。
「私の事を気に入らないのは構わない。しかし同盟を結ぶ以上、他国とも連携をとり、足並みを揃える必要があると思うのだ。その事をもう一度獅子王と話し合いたい。どうしてもというのならば、彼に同盟の主導権を握らせてもいい」
「…それは危険だ」
あの男は、ただの王ではない。
胸の内に、何かどす黒いものを感じる。
野心家で、傲慢で…暴君という肩書きさえ似合いそうである。
奴に同盟の手綱を握らせるのは、この地を真っ二つに分けた大戦に繋がる恐れすらある。
「わかっている。その為に獅子の国へ向かうのだ。何とか説得してみる」
真っ直ぐな眼差しで俺を見る乙女。
『私を信じろ』と。
その瞳が訴えていた。
「わかった…どうせお前は言い出したら聞かんからな」
「助かる。ついでに、獅子の国には私一人で行く。妙な警戒心を抱かせたくない」
乙女はまたも無謀な事を言い出した。
「何を言い出すかと思えば…そのような事は容認できぬ」
「別に戦に行くのではない。会談をするだけだ」
「あの男が、一人でノコノコやってきたお前に対してそれで済ませると思うか?」
お前は女なのだぞ、と。
俺は乙女をたしなめるが。
「女は女でも、戦乙女だ。そんじょそこらの男になど遅れは取らぬよ」
乙女は軽やかに笑って見せた。
「悪かった。ただの独り言だ、忘れてくれ」
気持ちを切り替えるように一つ大きく息を吐いて、乙女は表情を引き締めた。
「後日、獅子の国に向かおうと思う」
「獅子王のところへか?」
俺の言葉に乙女は頷いた。
「私の事を気に入らないのは構わない。しかし同盟を結ぶ以上、他国とも連携をとり、足並みを揃える必要があると思うのだ。その事をもう一度獅子王と話し合いたい。どうしてもというのならば、彼に同盟の主導権を握らせてもいい」
「…それは危険だ」
あの男は、ただの王ではない。
胸の内に、何かどす黒いものを感じる。
野心家で、傲慢で…暴君という肩書きさえ似合いそうである。
奴に同盟の手綱を握らせるのは、この地を真っ二つに分けた大戦に繋がる恐れすらある。
「わかっている。その為に獅子の国へ向かうのだ。何とか説得してみる」
真っ直ぐな眼差しで俺を見る乙女。
『私を信じろ』と。
その瞳が訴えていた。
「わかった…どうせお前は言い出したら聞かんからな」
「助かる。ついでに、獅子の国には私一人で行く。妙な警戒心を抱かせたくない」
乙女はまたも無謀な事を言い出した。
「何を言い出すかと思えば…そのような事は容認できぬ」
「別に戦に行くのではない。会談をするだけだ」
「あの男が、一人でノコノコやってきたお前に対してそれで済ませると思うか?」
お前は女なのだぞ、と。
俺は乙女をたしなめるが。
「女は女でも、戦乙女だ。そんじょそこらの男になど遅れは取らぬよ」
乙女は軽やかに笑って見せた。
確かに。
俺でさえ乙女に一撃入れようと思えば相当な傷を覚悟せねばならぬ。
獅子王がどれ程の武術の腕か知らぬが、完全な防御にまわった乙女には傷一つ付けられはすまい。
「くれぐれも用心しろ。奴は危険だ」
「わかっている。紅は心配性なのだな」
そう言って乙女は玉座を立った。
「今日は少し疲れた。もう休む事にする」
そう、乙女ならば傷一つ付けられはすまい。
心に何の迷いもない、いつもの乙女だったのならば…。
俺でさえ乙女に一撃入れようと思えば相当な傷を覚悟せねばならぬ。
獅子王がどれ程の武術の腕か知らぬが、完全な防御にまわった乙女には傷一つ付けられはすまい。
「くれぐれも用心しろ。奴は危険だ」
「わかっている。紅は心配性なのだな」
そう言って乙女は玉座を立った。
「今日は少し疲れた。もう休む事にする」
そう、乙女ならば傷一つ付けられはすまい。
心に何の迷いもない、いつもの乙女だったのならば…。
獅子の国は、女神国から北に半日ほど向かった先にある、山沿いの大きな国だ。
主な産業は、鉄鋼。
鉱山を持っている事もあり、武器や鎧、農民が使う鍬や鋤、果ては鍋やフォークに至るまで、東方の鉄製品の殆どはこの国が賄っている。
当然国の規模も女神国とは桁違いで、軍事力もそれに比例する。
八十万という兵数は、この地の軍事力としてもかなりの上位に位置するのではなかろうか。
私は早速その日、獅子王との会談の為に獅子の国へと向かっていた。
…獅子の国の砦門前まで馬を走らせると。
「お待ちしておりました、女神国女王陛下」
既に連絡が届いていた事もあり、獅子の国の騎士が出迎えに来ていた。
王宮までの足として、馬車まで準備している徹底振りだ。
「獅子王は王宮にてお待ちです。早速ご案内いたします。どうぞこちらへ」
馬車の中へとすすめられる。
馬車は静かに走り始めた。
御者も馬もよく訓練されている。
不快な揺れなど殆ど感じさせなかった。
…馬車の窓から街の様子を見る。
流石は鉄鋼で潤っている国だ。
民衆の身なりも、女神国より一段階上といった印象を受ける。
馬車の中で騎士に振る舞われた紅茶は私の好きな銘柄の茶葉で、とても美味しく感じた。
その紅茶を飲み終える頃。
「見えてきました。あれが獅子の国の王宮です」
騎士が窓の外を見ながら言う。
…そこから見えるのは、最早王宮というよりは要塞だった。
女神国の王宮も改装を終えてかなり広くなったが、獅子の国の王宮はそれを遥かに上回る。
本来の王城のそばに隣接して幾つもの小塔が建てられ、見ようによっては無計画に建築されているようにも感じられる。
…王宮の中には、絢爛豪華にする事で自国の権力を誇示するものもあれば、敵に攻め込まれた時に簡単に玉座にたどり着けぬように、わざと複雑な構造になっているものもある。
獅子の国の王宮は恐らく後者なのだろう。
主な産業は、鉄鋼。
鉱山を持っている事もあり、武器や鎧、農民が使う鍬や鋤、果ては鍋やフォークに至るまで、東方の鉄製品の殆どはこの国が賄っている。
当然国の規模も女神国とは桁違いで、軍事力もそれに比例する。
八十万という兵数は、この地の軍事力としてもかなりの上位に位置するのではなかろうか。
私は早速その日、獅子王との会談の為に獅子の国へと向かっていた。
…獅子の国の砦門前まで馬を走らせると。
「お待ちしておりました、女神国女王陛下」
既に連絡が届いていた事もあり、獅子の国の騎士が出迎えに来ていた。
王宮までの足として、馬車まで準備している徹底振りだ。
「獅子王は王宮にてお待ちです。早速ご案内いたします。どうぞこちらへ」
馬車の中へとすすめられる。
馬車は静かに走り始めた。
御者も馬もよく訓練されている。
不快な揺れなど殆ど感じさせなかった。
…馬車の窓から街の様子を見る。
流石は鉄鋼で潤っている国だ。
民衆の身なりも、女神国より一段階上といった印象を受ける。
馬車の中で騎士に振る舞われた紅茶は私の好きな銘柄の茶葉で、とても美味しく感じた。
その紅茶を飲み終える頃。
「見えてきました。あれが獅子の国の王宮です」
騎士が窓の外を見ながら言う。
…そこから見えるのは、最早王宮というよりは要塞だった。
女神国の王宮も改装を終えてかなり広くなったが、獅子の国の王宮はそれを遥かに上回る。
本来の王城のそばに隣接して幾つもの小塔が建てられ、見ようによっては無計画に建築されているようにも感じられる。
…王宮の中には、絢爛豪華にする事で自国の権力を誇示するものもあれば、敵に攻め込まれた時に簡単に玉座にたどり着けぬように、わざと複雑な構造になっているものもある。
獅子の国の王宮は恐らく後者なのだろう。
王宮の前に馬車を横付けされ、私は入り口の前に降りた。
「どうぞこちらへ」
騎士に案内されて玉座の間に向かったものの、とても一人で帰る自信がないほどの複雑な道順だった。
何度曲がり角を曲がったか、既に記憶があやふやになる頃。
「こちらでございます」
騎士は一際大きな、黄金の装飾の施された扉の前に立ち止まった。
「獅子王、女神国の女王陛下をお連れ致しました」
「入れ」
野太い声が聞こえる。
「どうぞ」
騎士が扉を開く。
…長い長い絨毯敷きの玉座の間の突き当たりに。
「よく来たな、戦乙女殿」
玉座に頬杖をついて座り、膝を組んで不敵な笑みを浮かべる獅子王の姿があった。
「突然の会談に応じて頂き、感謝する」
二、三歩歩み出て、私は王族流の挨拶をする。
「して、用件は何だ」
「先日の同盟の件だ」
私は真っ直ぐに獅子王を見て言った。
「貴方が私に対していい感情を抱いていないのはよくわかった。その事に対して文句はないし、苦言を言うつもりもない。だが、同盟は私と獅子王個人の事ではなく、国と国との問題だ。どうか快く同盟に参加してはいただけぬか」
「何を言うかと思えば」
獅子王は笑った。
「どうぞこちらへ」
騎士に案内されて玉座の間に向かったものの、とても一人で帰る自信がないほどの複雑な道順だった。
何度曲がり角を曲がったか、既に記憶があやふやになる頃。
「こちらでございます」
騎士は一際大きな、黄金の装飾の施された扉の前に立ち止まった。
「獅子王、女神国の女王陛下をお連れ致しました」
「入れ」
野太い声が聞こえる。
「どうぞ」
騎士が扉を開く。
…長い長い絨毯敷きの玉座の間の突き当たりに。
「よく来たな、戦乙女殿」
玉座に頬杖をついて座り、膝を組んで不敵な笑みを浮かべる獅子王の姿があった。
「突然の会談に応じて頂き、感謝する」
二、三歩歩み出て、私は王族流の挨拶をする。
「して、用件は何だ」
「先日の同盟の件だ」
私は真っ直ぐに獅子王を見て言った。
「貴方が私に対していい感情を抱いていないのはよくわかった。その事に対して文句はないし、苦言を言うつもりもない。だが、同盟は私と獅子王個人の事ではなく、国と国との問題だ。どうか快く同盟に参加してはいただけぬか」
「何を言うかと思えば」
獅子王は笑った。
「同盟には参加してやらんでもない。そう言った筈だ」
玉座の背もたれに寄りかかる獅子王。
「だが、独自の判断で行動すると仰っていた。それでは困る。同盟を結んだ以上、他国とも足並みを揃えてもらわねば」
「たかだか兵数十万程度の国とか?」
私の言葉を、獅子王は一笑に付した。
「我が国は単独でも大抵の敵と渡り合える。別に同盟など結ばずともな。今回の同盟、貴様らにとっては妙案かもしれぬが、獅子の国にとっては何の旨みもないのだ。ただ厄介なお守りが増えるだけでな」
「……」
確かにそう言われれば、こちらとしては返す言葉もない。
「だが…」
獅子王はニヤリと笑う。
「乙女、貴様のその案には少し感心もしていた所だ」
「感心?」
私は問い返す。
「そうとも…綺麗事や理想ばかり並べ、いつまで経っても女王の自覚芽生えぬ貴様に正直いらついてもいたが…やっと世渡りというものを覚えたらしい」
彼は私を見下ろすように言った。
「長いものには巻かれよ。寄らば大樹の陰…強い者に取り入り、庇護を受けるという事を覚えたか」
「な…に…!?」
その言葉に、私は憤った。
「ならば取り入る時には手土産の一つも必要な事ぐらい、貴様もわかっただろう?何を持ってきた。手ぶらな所を見るに…貴様のその身が手土産か?」
玉座の背もたれに寄りかかる獅子王。
「だが、独自の判断で行動すると仰っていた。それでは困る。同盟を結んだ以上、他国とも足並みを揃えてもらわねば」
「たかだか兵数十万程度の国とか?」
私の言葉を、獅子王は一笑に付した。
「我が国は単独でも大抵の敵と渡り合える。別に同盟など結ばずともな。今回の同盟、貴様らにとっては妙案かもしれぬが、獅子の国にとっては何の旨みもないのだ。ただ厄介なお守りが増えるだけでな」
「……」
確かにそう言われれば、こちらとしては返す言葉もない。
「だが…」
獅子王はニヤリと笑う。
「乙女、貴様のその案には少し感心もしていた所だ」
「感心?」
私は問い返す。
「そうとも…綺麗事や理想ばかり並べ、いつまで経っても女王の自覚芽生えぬ貴様に正直いらついてもいたが…やっと世渡りというものを覚えたらしい」
彼は私を見下ろすように言った。
「長いものには巻かれよ。寄らば大樹の陰…強い者に取り入り、庇護を受けるという事を覚えたか」
「な…に…!?」
その言葉に、私は憤った。
「ならば取り入る時には手土産の一つも必要な事ぐらい、貴様もわかっただろう?何を持ってきた。手ぶらな所を見るに…貴様のその身が手土産か?」
「愚弄するな!!」
他国の、しかも玉座の間である事も忘れて私は吠えた。
「私は同盟の為に来たのだ!貴様の庇護を受けに来た訳でもなければ、貴様より格下のつもりもない!同盟とは同格の者同士の事を言うのだ!」
「ほぅ…?」
獅子王は嘲りの目を私に向ける。
「大国や黒の旅団を壊滅させた程度で、随分のぼせ上がっているようだな、乙女」
「…!!」
こいつ、黒の旅団との戦いの事まで知っている?
あの戦いは国外には漏らさぬように内密にしていたというのに。
「他国の情報収集も戦のうちだぞ。まだまだ自覚が足りんな、女王陛下」
そう言って獅子王は玉座から立ち上がった。
「乙女…この世には貴様程度の力ではどうにもならぬ、圧倒的な実力差というものがあるのだ。例えば獅子の国と女神国、貴様と俺のようにな」
「…そのような話を始めるつもりならば帰らせてもらう」
私は獅子王に背を向ける。
が。
「待たぬか」
獅子王は私の腕をつかんだ。
馬鹿な…先程まで玉座の前にいたのに…一瞬にして間合いを詰めたのか。
しかも。
「くっ…」
この剛力…つかまれた腕が痛い。
「乙女…その頭の固さは如何ともし難いが…俺はお前を高く買っているのだぞ?」
獅子王はそう言って、私の体を舐め回すように見た。
「女としてな」
他国の、しかも玉座の間である事も忘れて私は吠えた。
「私は同盟の為に来たのだ!貴様の庇護を受けに来た訳でもなければ、貴様より格下のつもりもない!同盟とは同格の者同士の事を言うのだ!」
「ほぅ…?」
獅子王は嘲りの目を私に向ける。
「大国や黒の旅団を壊滅させた程度で、随分のぼせ上がっているようだな、乙女」
「…!!」
こいつ、黒の旅団との戦いの事まで知っている?
あの戦いは国外には漏らさぬように内密にしていたというのに。
「他国の情報収集も戦のうちだぞ。まだまだ自覚が足りんな、女王陛下」
そう言って獅子王は玉座から立ち上がった。
「乙女…この世には貴様程度の力ではどうにもならぬ、圧倒的な実力差というものがあるのだ。例えば獅子の国と女神国、貴様と俺のようにな」
「…そのような話を始めるつもりならば帰らせてもらう」
私は獅子王に背を向ける。
が。
「待たぬか」
獅子王は私の腕をつかんだ。
馬鹿な…先程まで玉座の前にいたのに…一瞬にして間合いを詰めたのか。
しかも。
「くっ…」
この剛力…つかまれた腕が痛い。
「乙女…その頭の固さは如何ともし難いが…俺はお前を高く買っているのだぞ?」
獅子王はそう言って、私の体を舐め回すように見た。
「女としてな」
獅子王の腕を振りほどこうとするが、びくともしない。
「その統率力に加えて可憐さ、美貌…国の象徴としても素晴らしいし、その身を自由にできる事は、男としても征服欲を満たされる…」
獅子王は私の体を引き寄せた。
「お前はわかっておらぬのだ。甲冑などよりもドレス…ドレスよりも、一糸纏わぬ姿の方が、お前の美しさは引き立つ」
「黙れ!!」
空いていたもう片方の手で、私は獅子王の顔を握り拳で殴りつけた!!
それでも。
「力ずくというのは嫌いでな」
獅子王は涼しい顔をしていた。
「国を挙げてまで女神国を陥落させ、貴様を奪い取るというのは少々気が乗らなかった。そう思っていた矢先の、貴様からの同盟話だ。これは使えると思った。案の定貴様は俺を説得しようとノコノコここまでやって来た。信義の証のつもりか知らぬが、あの腕利きの紅まで置いてくる馬鹿正直ぶりでな」
臭い息を吐きかけながら獅子王は笑う。
「その頭の悪さ加減と夢見がちな性格は矯正でもすれば何とかなるだろう…乙女、望み通り同盟も結ぶし、女神国も守ってやる…お前の身ひとつでな。安いものだろう?」
「ぐ…!!」
獅子王の腕の中で、締め付けが強くなる。
息苦しくなり、意識が朦朧とする。
いかん、逃げなければ…。
逃げ…。
「くれ…な…」
最後に浮かんだのは紅の無表情。
そこから先は、もう覚えていなかった。
「その統率力に加えて可憐さ、美貌…国の象徴としても素晴らしいし、その身を自由にできる事は、男としても征服欲を満たされる…」
獅子王は私の体を引き寄せた。
「お前はわかっておらぬのだ。甲冑などよりもドレス…ドレスよりも、一糸纏わぬ姿の方が、お前の美しさは引き立つ」
「黙れ!!」
空いていたもう片方の手で、私は獅子王の顔を握り拳で殴りつけた!!
それでも。
「力ずくというのは嫌いでな」
獅子王は涼しい顔をしていた。
「国を挙げてまで女神国を陥落させ、貴様を奪い取るというのは少々気が乗らなかった。そう思っていた矢先の、貴様からの同盟話だ。これは使えると思った。案の定貴様は俺を説得しようとノコノコここまでやって来た。信義の証のつもりか知らぬが、あの腕利きの紅まで置いてくる馬鹿正直ぶりでな」
臭い息を吐きかけながら獅子王は笑う。
「その頭の悪さ加減と夢見がちな性格は矯正でもすれば何とかなるだろう…乙女、望み通り同盟も結ぶし、女神国も守ってやる…お前の身ひとつでな。安いものだろう?」
「ぐ…!!」
獅子王の腕の中で、締め付けが強くなる。
息苦しくなり、意識が朦朧とする。
いかん、逃げなければ…。
逃げ…。
「くれ…な…」
最後に浮かんだのは紅の無表情。
そこから先は、もう覚えていなかった。
「何?」
乙女不在の間に国の留守を預かっていた俺は、獅子の国からの使者の言葉を聞いて耳を疑う。
「同盟は成立いたしました。貴国の女王陛下は同盟の全権を獅子王に委譲、西方諸国との会談の為、単身西へと向かわれました」
玉座の間で片膝をついた獅子の国の使者は、恥ずかしげもなくそんな伝言を伝えた。
「馬鹿な!」
「そのようなたわけた話を信じろというのか!!」
臣下の者たちは激怒する。
当然だ。
乙女が俺達に一言もなく、そのような判断を下すわけがない。
それにああ見えて、乙女は女神国の事を何よりも案じている。
その国を放って単身西へと向かうなど有り得ない。
そのような任務であれば俺に命じる筈だ。
「私に怒鳴られましても…私はただ事実を女神国の皆様にお伝えするよう託(ことづか)って来ただけでして…」
ニヤリと笑みを浮かべる使者。
こいつ、獅子王の子飼いか。
大した役者ぶりだ。
「よかろう。伝言ご苦労だった」
俺の言葉に、他の者達がギョッとした。
「よいのですか!?紅様!?」
「事実を伝えにきたというのだ。これ以上何をする必要がある」
俺は表情一つ変えずに言う。
「それではこれにて失礼致します」
スゴスゴと引き下がる使者。
その使者に。
「おいお前」
俺は冷徹な眼を向けた。
「『事実』を伝えにきたのだな…?一つでも偽りがあった場合は外交問題だぞ…獅子王にも伝えておけ…」
乙女不在の間に国の留守を預かっていた俺は、獅子の国からの使者の言葉を聞いて耳を疑う。
「同盟は成立いたしました。貴国の女王陛下は同盟の全権を獅子王に委譲、西方諸国との会談の為、単身西へと向かわれました」
玉座の間で片膝をついた獅子の国の使者は、恥ずかしげもなくそんな伝言を伝えた。
「馬鹿な!」
「そのようなたわけた話を信じろというのか!!」
臣下の者たちは激怒する。
当然だ。
乙女が俺達に一言もなく、そのような判断を下すわけがない。
それにああ見えて、乙女は女神国の事を何よりも案じている。
その国を放って単身西へと向かうなど有り得ない。
そのような任務であれば俺に命じる筈だ。
「私に怒鳴られましても…私はただ事実を女神国の皆様にお伝えするよう託(ことづか)って来ただけでして…」
ニヤリと笑みを浮かべる使者。
こいつ、獅子王の子飼いか。
大した役者ぶりだ。
「よかろう。伝言ご苦労だった」
俺の言葉に、他の者達がギョッとした。
「よいのですか!?紅様!?」
「事実を伝えにきたというのだ。これ以上何をする必要がある」
俺は表情一つ変えずに言う。
「それではこれにて失礼致します」
スゴスゴと引き下がる使者。
その使者に。
「おいお前」
俺は冷徹な眼を向けた。
「『事実』を伝えにきたのだな…?一つでも偽りがあった場合は外交問題だぞ…獅子王にも伝えておけ…」
この作品のキーワード
この作家の他の作品
表紙を見る
この宇宙のどこかにいるかもしれない
某宇宙人の
ちょっと真面目な
そっくりさんコメディ
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…