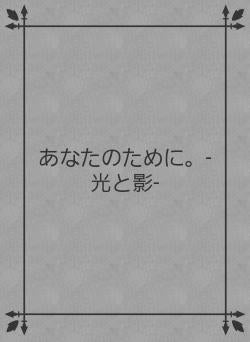それはあまりにも素早くて、頭で理解するのに遅くなってしまった。
傷口が塞がったか三篠に聞こうとしたのに、三篠は急に起き上がって……
頭が理解した時には、三篠は私の手首に吸いついて血を吸っていた。
「……小雛……小雛……」
「…ん、ちょっ…と……みさ、き…」
後ろに下がろうとすると、三篠の腕が私の腰に回ってきた。
あまりの力強さに私の体は後ろへとゆっくり倒れていく。
いやらしい音をたてて、私の手首に吸いつく三篠。
くすぐったい反面、切ったところがチクッと痛い。
でもなんでだろう。
嫌だなんて思わずに、堪えるように三篠の腰に片腕を回してる自分がいる。
三篠が無事で良かった嬉しさと、初めて味わう痛みが混じって涙が出てきた。
私、いつの間にこんなに三篠のことばかり考えるようになってたんだろう。
毎日毎日三篠のことばかり考えて、会えないとこんなに寂しく思ってたなんて。
…あぁ、そうか。
私、好きになっていたんだね、三篠のこと。
一目見た時から、美しい人だと思ったあの時から私は三篠に惚れていたのかもしれない。
やっぱ特殊な家系に生まれたから、惚れる相手もちょっと変わった人になってしまった。
でもこれが私の運命なら、それに従ってもいいかもしれない。
私はこのまま紅葉が帰って来る前に、意識を手放した……ーーーーーー