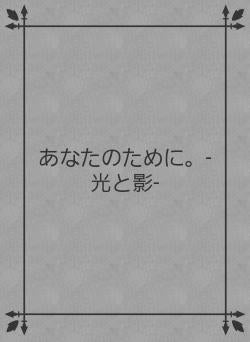「『あいつを守れるくらいに強くなりたいんだ。妖王になってあいつを、小雛を傷つけないように強くなる。そのためだったらこんな修行、苦じゃねぇよ』と言っておりました」
その時三篠の言った言葉のままに、深寿さんは教えてくれた。
そのせいかな。
三篠の言ったところだけ、三篠の声で聞こえた気がしたのは。
三篠は小さい時から私だけを見て、私のために頑張ってくれたんだ。
お礼を言っても、言いきれないよ。
ううん、お礼なんて言葉じゃダメなんだ。
私は鵺姫として妖王となる三篠の力になって、お礼を返すんだ。
何かの決意を固めている小雛を深寿は、どこか悲しそうに見ていた。
「…三篠が羨ましいわ。こんなにも相手に想われ、三篠も相手のことを想っていて…
わたくしも出来るのなら、そうしたい」
深寿さんが誰かを想いながら見上げた星空は先程と変わらないが、深寿には暗く見えた。
そう深寿が感じたことも、小雛は気付くはずもなかった。
そしてこの話を隣の男湯に入っていた三篠が頬を赤くしながら聞いていたことも、気付かなかった。
「……くそ、深寿の奴……覚えておけよ」
三篠は恥ずかしさを隠すようにして、静かに頭までお湯に沈んだ。