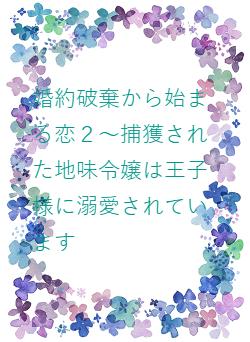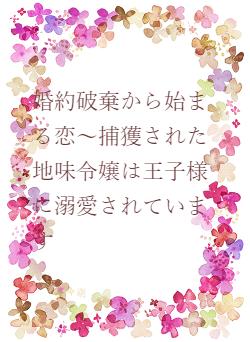「はい、お待たせ」
陽菜がコーヒーとクッキーを運んでくれた。
その動作も自然で手慣れていることが分かる。
コーヒーカップもクッキー皿も有名なブランド品だった。
陽菜は自分の前にカップを置くと、目の前に座った。
テーブルを挟んでいるとはいえ、正面に陽菜がいるって、どうなんだろう。
おまけに2人きりだし、緊張してきた。ドキドキする。
でも、なんか話さないと。
俺は陽菜の手元に目をやった。
「あれ、陽菜は食べないの?」
彼女の所には、カップ一つだけ。
「うん。匂いだけでお腹いっぱいになっちゃった。白河くんは食べてね。口にあうかわかんないけど」
作ってもらう側だからよくわかんないけど、そういうもんなんだろうか。
食べるのがもったいないくらいだけど、
せっかく陽菜が作ってくれたものだから遠慮せずに食べよう。
陽菜がコーヒーとクッキーを運んでくれた。
その動作も自然で手慣れていることが分かる。
コーヒーカップもクッキー皿も有名なブランド品だった。
陽菜は自分の前にカップを置くと、目の前に座った。
テーブルを挟んでいるとはいえ、正面に陽菜がいるって、どうなんだろう。
おまけに2人きりだし、緊張してきた。ドキドキする。
でも、なんか話さないと。
俺は陽菜の手元に目をやった。
「あれ、陽菜は食べないの?」
彼女の所には、カップ一つだけ。
「うん。匂いだけでお腹いっぱいになっちゃった。白河くんは食べてね。口にあうかわかんないけど」
作ってもらう側だからよくわかんないけど、そういうもんなんだろうか。
食べるのがもったいないくらいだけど、
せっかく陽菜が作ってくれたものだから遠慮せずに食べよう。