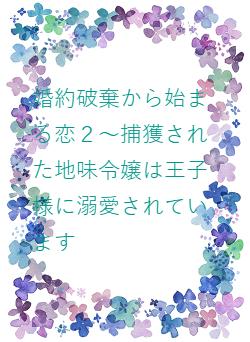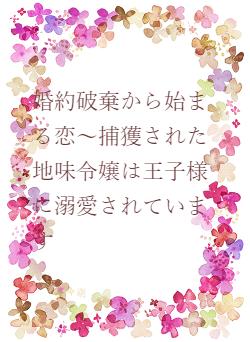「ねっ。冷たいでしょ。僕、すごく待ってたんだよ」
「そっか。ごめんね。ホント、冷たいね」
陽菜はすまなさそうな顔で、歩夢の手を両手で包んで。
まるで小さい子供にでもするように、温めてやってるようには見える。
今は2月。
ちょっと外に出れば、手なんかすぐに冷えることぐらいわかるだろ?
別に玄関で待ってなくても、陽菜の帰宅を確かめてから来ても遅くはないよな。
これ見よがしに、ここにいるあたり、なんかずる賢さを感じる。
わざと陽菜の同情を引いているようで。
「陽菜、ありがと。あったまったみたい。家の中、入ろうよ」
「そうだね」
陽菜はバッグから鍵を取り出した。
さっきから、こいつ俺の方を見ないな。
完全無視。
陽菜も陽菜だ。
2人の世界を作りやがって。
「そっか。ごめんね。ホント、冷たいね」
陽菜はすまなさそうな顔で、歩夢の手を両手で包んで。
まるで小さい子供にでもするように、温めてやってるようには見える。
今は2月。
ちょっと外に出れば、手なんかすぐに冷えることぐらいわかるだろ?
別に玄関で待ってなくても、陽菜の帰宅を確かめてから来ても遅くはないよな。
これ見よがしに、ここにいるあたり、なんかずる賢さを感じる。
わざと陽菜の同情を引いているようで。
「陽菜、ありがと。あったまったみたい。家の中、入ろうよ」
「そうだね」
陽菜はバッグから鍵を取り出した。
さっきから、こいつ俺の方を見ないな。
完全無視。
陽菜も陽菜だ。
2人の世界を作りやがって。